
体温調節の仕組み 脳と体で何が起きているの?
公開日2021.08.30
※当コンテンツの内容は2021年7月時点の情報となります。
私たちの体では、体温調節のためのさまざまな反応が無意識のうちに起こっています。その仕組みを詳しく調べると、同じ熱を作る反応でも、脳からの指令の通り道が異なることがわかってきました。
監修:中村和弘(名古屋大学大学院医学系研究科 総合医学専攻 統合生理学分野 教授 薬学博士)
目次
寒い時に熱を作る仕組みはどうなっているの?
無意識のうちに体温を調節しています
私たちの体では、皮膚にある温度センサーで寒さを感じると、脳にその情報が伝わり、熱を作る仕組みが無意識のうちに働いて、体温が低下しないようになっています。熱を作る仕組みは、寒さの程度に応じて次のように段階的に働きます。
(1)褐色脂肪細胞*で熱を作り、体温を下げないようにする
(2)それでも足りない時は骨格筋をブルブルふるわせて、さらに熱を作り、体温を下げないようにする(感染によって発熱した時にも起こる)
(1)も(2)も、自分がこうしようと思って起こすものではなく、無意識に起こる体温調節の反応で、「自律性体温調節」と呼ばれます。この二つの仕組みでは、脳からの指令の通り道が異なることが、最近の研究でわかってきました。
*褐色脂肪細胞とは:哺乳類の体内に存在する、熱を産生する能力を持つ特殊な脂肪細胞です。褐色脂肪細胞は「熱を作る」という単純な機能を通じて、生体の中の多様な調節や防御機構に寄与することがわかってきました。
通り道の違う2段階の仕組みで生命を維持
まず、少し寒い時は、脳からの指令で褐色脂肪細胞が熱を生み出します。この場合は、自律神経の一種である交感神経を通って、「熱を作れ」という指令が下されます。
それだけでは体温が保てないほど低温になって、とても寒くなると、脳の中の別のルートをたどり運動神経を介して「ふるえろ」という指令が骨格筋に届きます。その指令に基づき、骨格筋はブルブルふるえて、熱を生み出すという仕組みです。
ふるえによって、うまくしゃべったり、歩いたりすることができなくなることがありますが、体温が下がってしまうほど寒い時には、そうしたふだんの運動(随意運動)を犠牲にしても、体温を調節することのほうが、生命を維持するには優先されると考えられます。
体温調節にまつわる素朴な疑問
寒い時や熱が出る時に顔色が悪くなったり、手足が冷たくなったりするのはなぜ?
ふるえのほかにも、よく経験する体の反応で、体温調節が関係していることが、たくさんあります。
寒い時に体温の低下を防いだり、感染した時に体温を効率よく上げたり(発熱)するための仕組みとして、熱を逃がさないようにする反応があります。
皮膚表面近くの血管を収縮させて血流を低下させているのです。体の内部に血流を集め、体の外に熱が逃げるのを抑えています。
例えば、顔色が青白くなったり、手足が冷たくなったりするのは、この仕組みによるものです。
寒い時に鳥肌がたつのはなぜ?
犬や猫のように体毛が豊富にある動物では、寒さを感じた時に脳からの指令で立毛筋を収縮させて毛を立てると、ちょうど厚手のコートを着るのと同じように断熱の効果が高まり、体温が逃げにくくなります。
進化の名残で、人間でも同じように体毛が立つ反応が残っており、これが鳥肌です。ただし、残念ながら、体毛が少ないため、人間の鳥肌には、犬や猫のような断熱の効果はほとんどありません。
暑い時に汗をかくのはなぜ?
ヒトは汗をかくことで、体の表面がぬれます。この水分が蒸発する時に気化熱として体の熱をうばっていき、体表面の温度を低下させます。
ヒトはこのような方法で体を冷やすことができますが、犬や猫は、水状の汗を出す汗腺が退化しているため、暑い時に汗をかくことができません。その代わり、呼吸が速くなります。これは、気道の表面にある水分をたくさん蒸発させ、汗と同じように気化熱として体の熱を外へ逃がしているからです。
このように、いろいろな体の反応によって動物(哺乳類)は体温の調節をしています。

監修者紹介
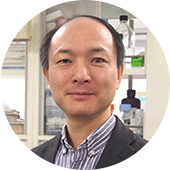
中村和弘
名古屋大学大学院医学系研究科 総合医学専攻 統合生理学分野 教授(薬学博士)
1997年京都大学薬学部卒業。2002年京都大学大学院薬学研究科博士後期課程修了。米国・オレゴン健康科学大学博士研究員、京都大学生命科学系キャリアパス形成ユニット准教授等を経て、2015年から現職。
- カテゴリ
- テーマ














