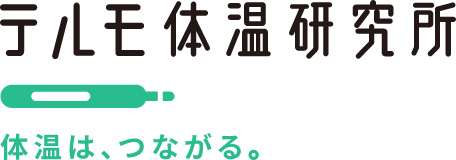平熱の変化にどう対応すればよいですか?
公開日2021.08.30
※当コンテンツの内容は2021年7月時点の情報となります。
高齢になると平熱が若いころとは違っていることがあります。何度か体温を測って現在の平熱を知っておきましょう。
監修:永島 計 早稲田大学人間科学学術院 体温・体液研究室 教授(医師、博士(医学))
目次
65歳をすぎたら平熱を測りなおしましょう
高齢者の体温は若い人より約0.2℃低くなっています
65歳以上の人の腋窩(ワキの下)で測定した体温は、10~50歳の人より0.2℃以上低くなっているという報告があります1)。
若いころの平熱が36.7℃だったとしても、いま高齢者になっているならもっと低い可能性が高いのです。若いころの平熱を基準にしていると、発熱した時に気づかなかったり、熱の程度を軽いと思ってしまったりする危険性があります。
感染症の発症を早い時期に知り、自分の体調を把握するうえでも、体温の定期的な測定は有用です。高齢になったら日ごろから体温を測り、自分の平熱を知っておくように心がけましょう。
1)入来ら:老人腋窩温の統計値.日老医誌12,172-177,1975
平熱は一つではありません
時間帯ごとの平熱は1日4回の検温で
体温は夜中や朝は低く、午後は高くというように1日のうちで変動します。 健康な状態の時、1日4回(起床時、午前、午後、夜)体温を測ってみましょう。食後すぐは体温が上がるので、食前や食間に検温するのが適切です。日を置いて何回か行い、平均値を出して時間帯ごとの平熱としておぼえておきましょう。
季節ごとの平熱も大事
高齢者は、暑さ、寒さに対する感度が鈍くなり、少しくらいの寒さや暑さでは体が反応しないこともあります。
ヒトは、寒い時は筋肉をふるわせて熱を生み出したり、皮膚血管を収縮させて熱を逃がさないようにしたりします。一方、暑い時は汗をかいて熱を放散したり、皮膚血管を拡張して熱を逃がしたりします。こうした反応が、高齢者は遅かったり、不十分だったり、不正確だったりするのです。
そのため、内部の体温が寒い時は低く、暑い時は高いところで安定してしまう傾向がみられます。
高齢者は、暑さ、寒さによる健康面への影響が若い人より大きいので、季節ごとに平熱を確認しておくほうがいいでしょう。
監修者紹介

永島 計
早稲田大学人間科学学術院 体温・体液研究室 教授(医師、博士(医学))
1985年京都府立医科大学卒業。京都府立医科大学附属病院研修医、修練医、大阪鉄道病院レジデントを経て、京都府立医科大学大学院博士課程(生理系)修了。京都府立医科大学助手、YALE大学医学部・John B Pierce研究所ポストドクトラルアソシエート、王立ノースショア病院オーバーシーフェロー、大阪大学医学部助手•講師、早稲田大学助教授を経て、2004年から現職。日本スポーツ協会スポーツドクター、日本医師会認定産業医。
- カテゴリ
- テーマ