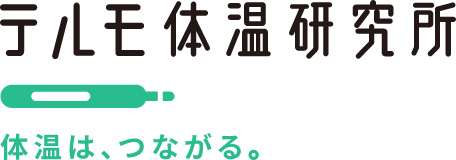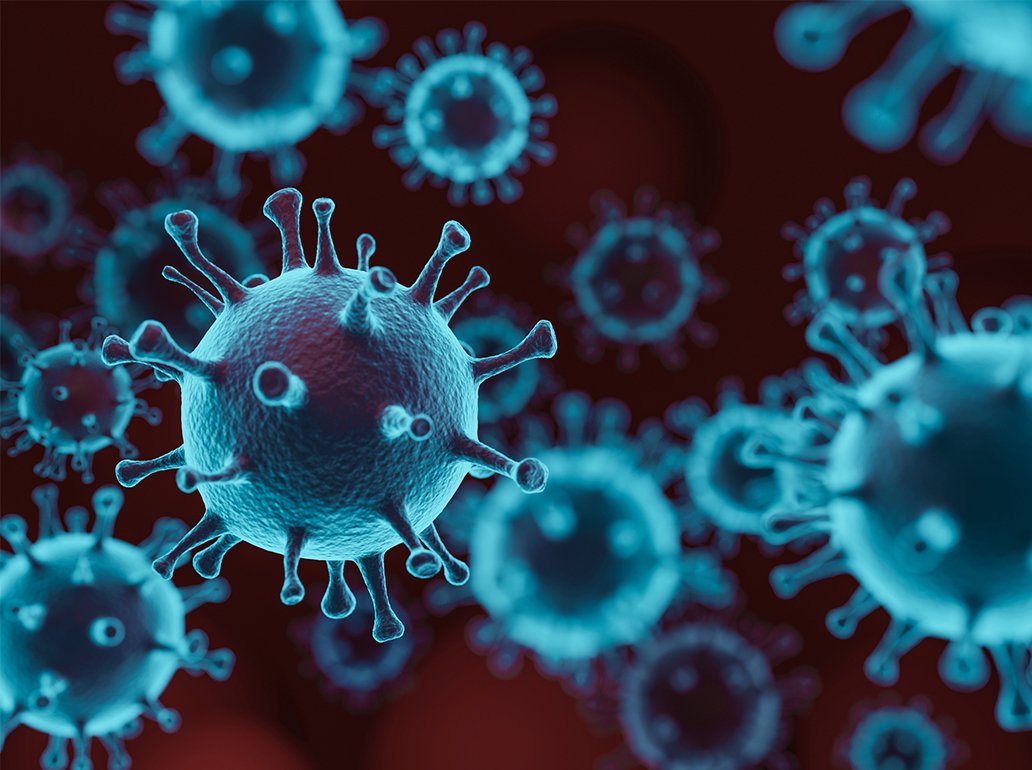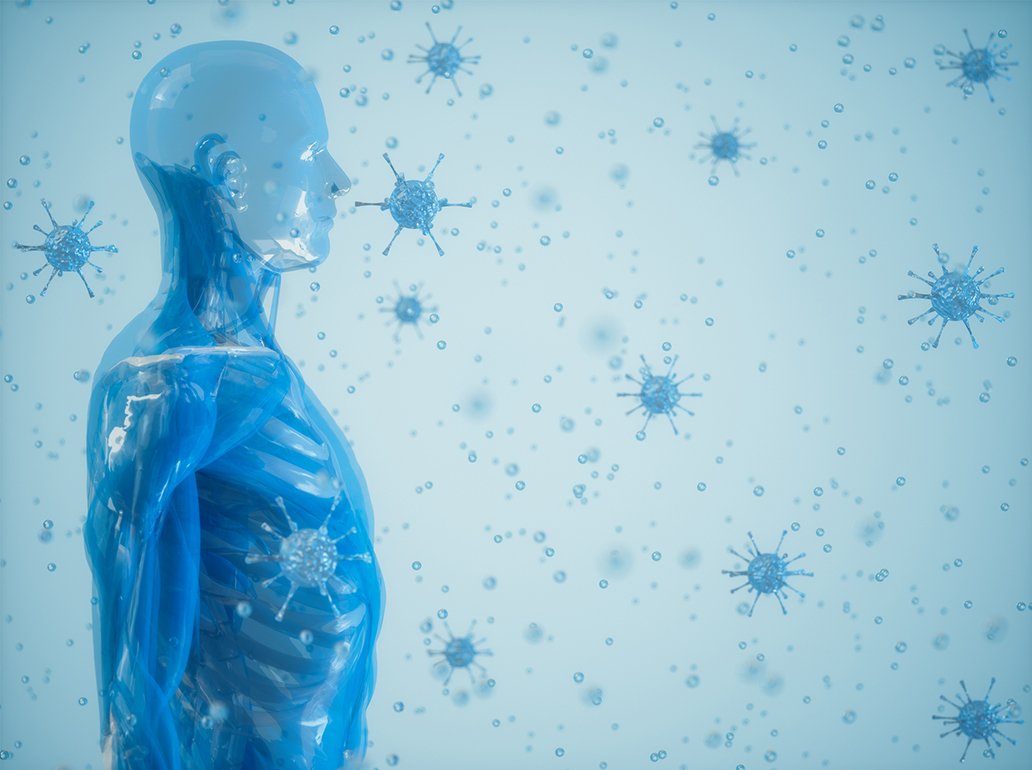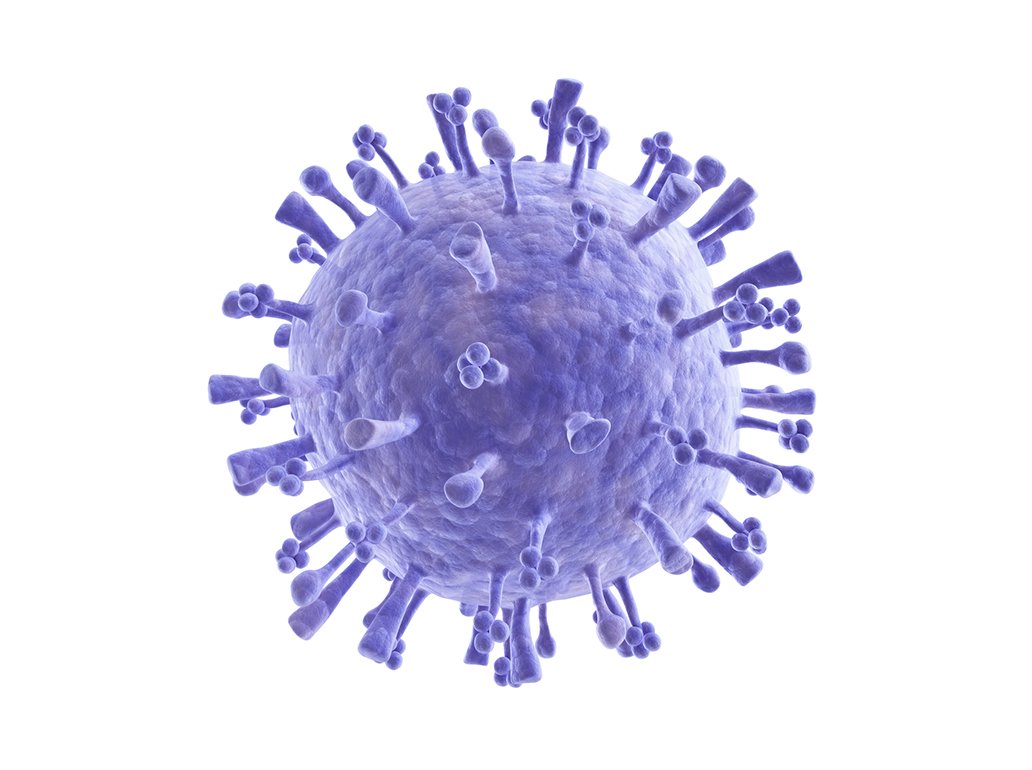大人の発熱
公開日2021.08.30
※当コンテンツの内容は2021年7月時点の情報となります。
発熱を伴う大人の原因として代表的な病気は、感染症、炎症を起こす病気(自己免疫疾患など)、がんなどです。
監修:岡部信彦(川崎市健康安全研究所 参与)
病原体の感染に伴い、発熱が
外敵を追いはらう免疫は、体温の上昇で活発に
発熱とは、体温が上昇している状態のことを指します。通常、37.5℃以上を発熱としていますが、平熱(体温)は一人ひとり違うので、何度くらいでその人にとっての発熱になるかについては、個人差があります。
発熱の原因として、代表的なものは以下の三つです。
・病原体(細菌やウイルス)の感染
・炎症を起こす病気(自己免疫疾患など)
・がん
病原体の感染に際して起こる体温の上昇は、敵である病源体と戦っている証でもあり、体温が上昇することによって免疫の働きを活発にしたりしている、一種の生体防御反応でもあります。
炎症を起こす病気の代表は自己免疫疾患
自己免疫疾患とは、免疫の働きをする細胞が自分の細胞や組織を誤って敵とみなしてしまい、攻撃する病気です。攻撃を受けた場所で炎症が起こり、炎症に伴って体温が上昇します。
たとえば、関節リウマチは自己免疫疾患の代表的な病気です。自己免疫疾患は、攻撃を受ける場所がさまざまであり、病気の種類も少なくありませんが、主に繰り返す発熱、全身の倦怠感、関節の痛みや腫れ、皮膚の赤みなどの症状が現れます。
がんのなかでは血液系のがんに多い腫瘍熱
がんの症状の一つとして、繰り返す発熱がみられることがあります。これを腫瘍熱といいます。
どのがんでも腫瘍熱を起こす可能性はありますが、血液系のがんである白血病や悪性リンパ腫で多いとされています。
そのほか、薬剤の副作用、アレルギー反応、物理的・化学的な刺激に対する反応、心因性や環境の影響などによって体温が上昇することがあります。
大人が発熱したときに、疑われる病気や原因はさまざまですが、主なものをまとめました。
表1 発熱を主な症状とする大人の病気
| 発熱の原因 | 病名 | 病気の起こり方、症状 |
|---|---|---|
| 感染症 | 扁桃炎 | のどの奥の扁桃が細菌に感染して起こる。のどの赤い腫れや激しい痛み、高熱、倦怠感など |
| 咽頭炎 | のどの粘膜が細菌やウイルスに感染して起こる。のどの痛み、頭痛、発熱など | |
| 肺炎 | 肺にウイルスや細菌が感染して起こる。かぜやインフルエンザが長引き重症化した結果起こる。 免疫力の低下した人、高齢者に起こりやすい。発熱、せき、息苦しさなど | |
| 急性腎盂腎炎 | 腎盂(尿管と接続し、尿をためておく部分)や腎そのものに細菌が感染して起こる。悪寒、発熱、尿の濁りや血尿、背中から腰にかけての痛みなど | |
| 急性胆のう炎、急性胆管炎 | 胆のうや胆管に細菌が感染して起こる。胆道炎ともいう。上腹部の激しい痛み、高熱、吐き気など | |
| 急性肝炎 | ウイルス感染を原因とするものがA、B、C、D、E型の5種類確認されている1)。発熱、のどの痛み、頭痛など、かぜに似た症状ではじまる | |
| 腹膜炎 | 腹膜が細菌に感染して起こる。急性虫垂炎や胃・十二指腸潰瘍などで胃や腸に穴があいたりすることで起こりやすい。激しい腹痛、高熱、吐き気、嘔吐など | |
| 脳炎 | 脳に炎症が起こる病気。ウイルス、細菌、真菌(カビ)、寄生虫といった病原体が脳に感染して起こる「感染性脳炎」と、自己免疫によって起こる「自己免疫性(免疫介在性)脳炎」がある。頭痛、発熱、意識障害、けいれんなど | |
| 髄膜炎 | 脳や脊髄をおおう髄膜に炎症が起こる病気。細菌が感染して起こる「細菌性髄膜炎」は、肺炎球菌、インフルエンザ菌などが原因。発熱や頭痛、嘔吐、項部硬直(首が痛みを伴って硬くなり、胸の前のほうに曲がらなくなる状態)など | |
| 肛門周囲膿瘍 | 直腸から肛門の周囲の粘膜が傷つき、大腸菌などの細菌が感染して起こる。痔ろうの初期段階。肛門周囲のしこり、腫れ、痛み、高熱、悪寒、吐き気など | |
| 食中毒 | 主に黄色ブドウ球菌、腸管出血性大腸菌、ノロウイルスなどの細菌やウイルスを含んだ食べ物によって起こる。激しい下痢、腹痛、嘔吐。熱の程度はさまざま | |
| 輸入感染症 (ジカ熱、デング熱など) |
ジカウイルス、デングウイルスなど、日本に存在しない細菌やウイルスなどに海外で感染したり、海外から持ち込まれたりすることで発生する | |
| 炎症性疾患 | 自己免疫疾患 (関節リウマチ・SLE2)など) |
免疫の働きをする細胞が、自分の細胞、組織を敵だと思って攻撃することで全身のさまざまな箇所に炎症が生じる病気 |
| がん | 白血病・悪性リンパ腫など | がん自体が繰り返す発熱の原因となる(腫瘍熱)。血液系のがんで起こることが多い |
| 抜歯、外傷 | 抜歯や大きなけがのあとに起こる。腫れや膿みがあれば、感染の可能性も | |
| 薬剤熱 | 薬剤の副作用によって起こる | |
| 心因性発熱 | 急性または慢性のストレスによって体温が高くなる | |
| 環境(熱中症など) | 高温多湿の環境に長時間さらされ、体温が上昇し、体温調節機構のバランスが崩れて起こる | |
| 脱水 | 脱水により発熱することがある。同時に発熱時は、脱水症状に注意が必要となる | |
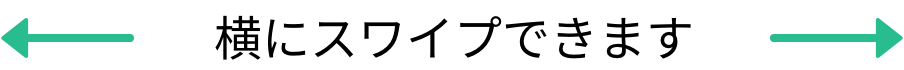
(テルモ作成)
1)日本では、D型はほとんどみられません。
2)全身性エリテマトーデス。
監修者紹介

岡部信彦
川崎市健康安全研究所 参与
1971年、東京慈恵会医科大学卒業。同大学小児科で研修後、帝京大学小児科助手、その後、慈恵医大小児科助手。国立小児病院感染科、神奈川県立衛生看護専門学校付属病院小児科などに勤務。1991~1994年、世界保健機関(WHO)西太平洋地域事務局(フィリピン・マニラ市)伝染性疾患予防対策課課長。1994~1997年、慈恵医大小児科助教授。1997年、国立感染症研究所感染症情報センター・室長。2000年、同研究所感染症情報センター長。2012年から川崎市健康安全研究所 所長に就任し、2024年より現職。内閣官房新型コロナウイルス感染症対策分科会委員、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード委員を歴任。
- カテゴリ
- テーマ