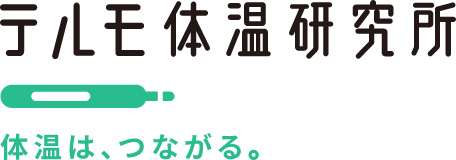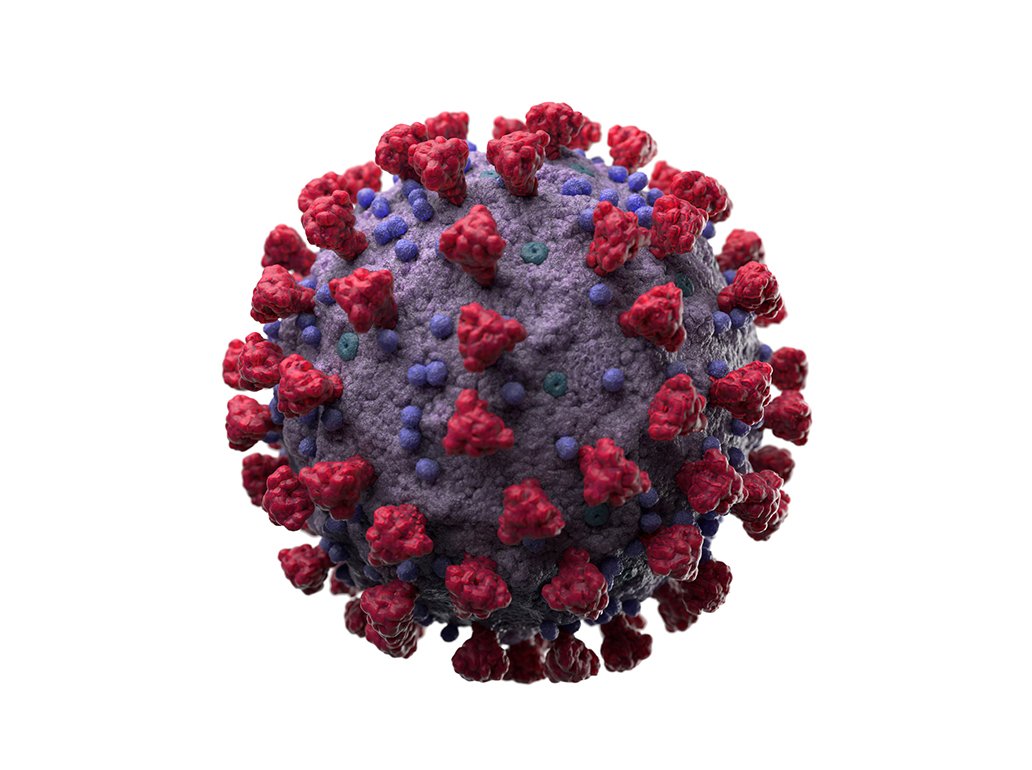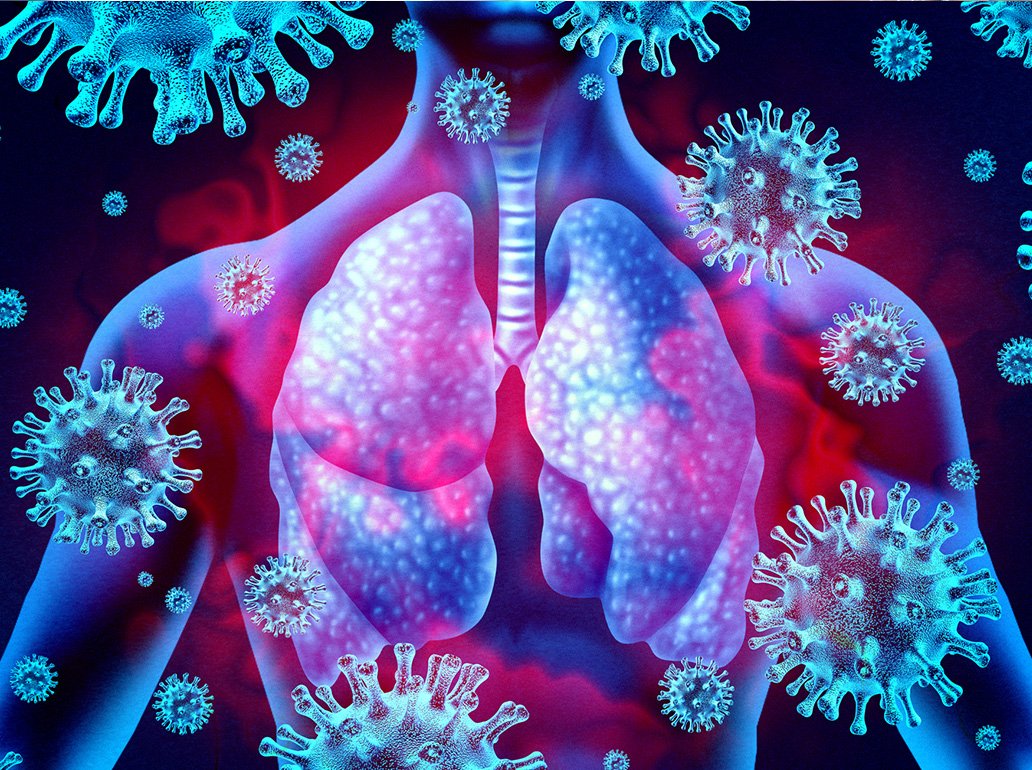- トップページ
- 発熱相談室
- 新型コロナウイルス感染症について
- 「新型コロナウイルス感染症」どうすれば防げる? 一人ひとりができること

「新型コロナウイルス感染症」どうすれば防げる? 一人ひとりができること
公開日2021.08.30
※当コンテンツの内容は2021年7月時点の情報となります。
新型コロナウイルス感染症を防ぐにはいくつかの基本となる対策があります。一人ひとりがその基本を守ることで、自分や自分の大切な人を感染から守ることができます。
監修:岡部信彦(川崎市健康安全研究所 参与)
ウイルスをできるだけ体に入れない
ウイルスの侵入経路に応じて、阻止
ウイルスは人の体に入り込み、そこで数を増やします。せきやくしゃみで外に出たウイルスがさらに、ほかの人の体に侵入する……。これを繰り返しながら、ウイルスは人から人へとその体を一時的なすみかとして、ウイルスの子孫を作り出していきます。
このようなウイルスの特徴を考えると、人と人との間を離す、人と会わないことが、究極の対策です。しかし、人と人が出会い、話をして、接触して人の社会が成り立っているので、完全に人と人とを離してしまうことは不可能であり、人の社会が消えてしまいます。
社会をある程度保ちながら感染の広がりを低く抑え込んでいく、そこのバランスが難しいところですが、感染の拡大の度合いによっては、国を挙げて一時、外出を制限し、社会生活を落としながら感染を抑え、落ち着きが見えてきたら少しずつ戻す、という対策が世界中で取られています。
なお、国内では「自粛」という形での生活の制限のお願いで一定の効果を上げてきていますが、そこには限界がある一方、海外では罰則を伴う形でのマスク着用、徹底的な外出禁止(ロックダウン)などが行われている国が多くみられ、どちらがより効果的で社会的に影響が少ないかなどについては議論が行われているところです。
一方、私たち一人ひとりが日常生活を送りながらできる対策は、感染症対策の基本としてとても大切です。ウイルスをできるだけ体に侵入させないこと、ウイルスが体に入り込むじゃまをする、そのすきを与えない、それが感染症予防の基本となります。
ウイルスなどの病原体が体に侵入する主な経路は、飛沫感染、エアロゾル感染、接触感染です。
飛沫感染は、せきやくしゃみ、つばにまぎれてウイルスが外に出て、そのウイルスをほかの人が吸い込むことで感染します。つまりせきやくしゃみ、つばがほかの人に届かなければ防ぐことができます。
マスクをつけることやせきエチケット(せきやくしゃみをするときにはハンカチや袖口で押さえるといったエチケット行為)、人との距離をとること(ソーシャルディスタンス)が基本的な対策となります。
また、閉鎖空間でのエアロゾル感染の可能性も指摘されています。エアロゾルとは、空気中を浮遊する液体や固体のごく小さな粒子と周囲の気体が混合したもので、状況によってマイクロ飛沫と呼ばれることもあります。新型コロナウイルスがこれに含まれていると、と、せきやくしゃみなどの飛沫より遠くまで飛散(1~2m以上)します。
そこで、閉鎖空間などでは飛沫が届く程度の距離から少し離れた人でも感染する可能性があると考えられています。そこで閉鎖空間での換気の重要性がさらに言われるようになりました。密閉された空間に多くの人が近接した距離で集まり、大声を発することなど、つまり三密の状態には常に注意が必要です1)。
この場合、換気をすることによって状況はかなり改善されます。なお、「三密を避ける」とは、三つの密が重なるとよりリスクが高まるという意味で、一つの密でもリスクはあるので、できるだけそのような環境を避けること、換気に注意することが、感染予防として大切なことです。
一方、接触感染は、手についたウイルスが口や目、鼻の粘膜を通してウイルスが体に入り込むものです。ついたウイルスは洗い流す(手洗い、うがい、顔を洗うなど)、できるだけ顔を触らないといったことが対策となります。
手洗いの仕方については、こちら。とくに物に触れやすい指先をきれいにしましょう。
1)厚生労働省 新型コロナウイルス感染症はこうした経路で広まっています
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000657104.pdf
とくに感染しやすい環境、三つの密を避ける
どんな環境だと感染が起こりやすいかの調査が進み、より注意しなければならない条件が明らかになっています。その条件とは、「三つの密」を避けることです。
三つの密とは
・換気の悪い密閉空間
・多数の人が集まる密集場所
・十分な距離がとれないなかで会話したり、大きな声を出したりする状況です。
・定期的に換気をする
・大人数での集まりは避ける
・会食や集まりではマスクを着け、大声での会話、長い時間のおしゃべりは避けることが対策となります。
三つの密は、一つでも感染の可能性が高まり、二つ、三つと重なるごとに危険性が大きくなるので、いずれも避けていくことが大切です。重ならなければ大丈夫、というわけではありません。

生活習慣を整えること、体調管理、検温、そして休む勇気
このほか、体に入ってきたウイルスと戦い、体を守る力(免疫力)を高めることも対策の一つとなります。よく眠り、栄養バランスのとれた食事に気を付け、適度な運動をすることが大切です。生活習慣を見直すことで、感染しても症状を抑えることができる可能性があります。
万一感染した時に、重症化リスクが高まるのは、糖尿病・肥満などの生活習慣病と言われるものです。日常からの健康管理が大変重要になります。
毎日決まった時間(たとえば朝起きた時)に体温を測り、自分の平熱を知ることも、自分の体の調子を知る第一歩です。検温をすることによって、体調の変化に早めに気づくことができます。
発熱、体がだるいといった不調があるときは、外出を控え、体を休めることが大切です。休む勇気を持つことは、自分の体を大切にし、感染を広げないための対策でもあります。
監修者紹介

岡部信彦
川崎市健康安全研究所 参与
1971年、東京慈恵会医科大学卒業。同大学小児科で研修後、帝京大学小児科助手、その後、慈恵医大小児科助手。国立小児病院感染科、神奈川県立衛生看護専門学校付属病院小児科などに勤務。1991~1994年、世界保健機関(WHO)西太平洋地域事務局(フィリピン・マニラ市)伝染性疾患予防対策課課長。1994~1997年、慈恵医大小児科助教授。1997年、国立感染症研究所感染症情報センター・室長。2000年、同研究所感染症情報センター長。2012年から川崎市健康安全研究所 所長に就任し、2024年より現職。内閣官房新型コロナウイルス感染症対策分科会委員、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード委員を歴任。
- カテゴリ
- テーマ
- キーワード