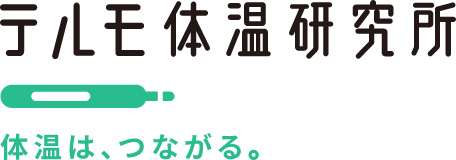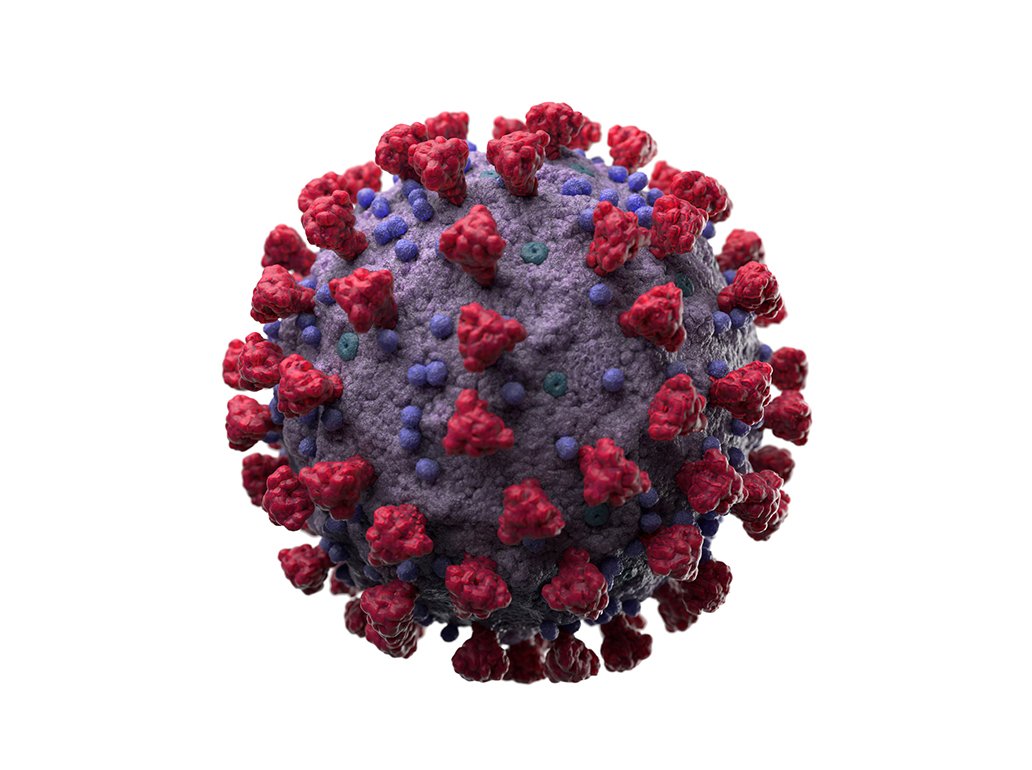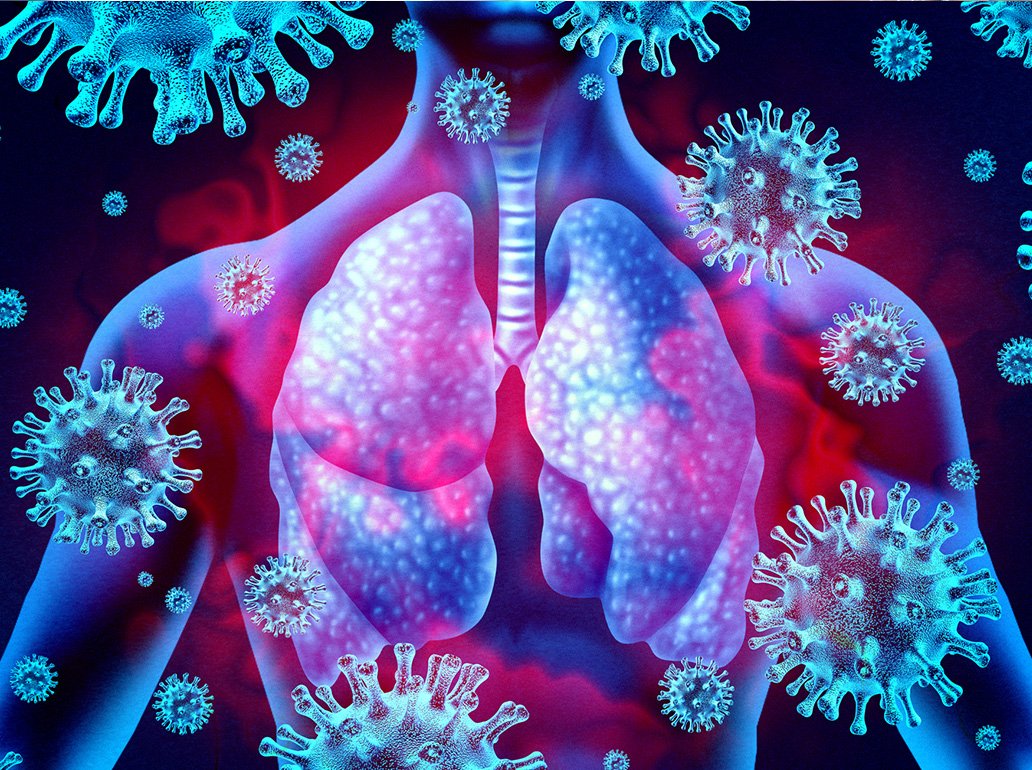- トップページ
- 発熱相談室
- 新型コロナウイルス感染症について
- 「新型コロナウイルス感染症」の診断、治療は?

「新型コロナウイルス感染症」の診断、治療は?
公開日2021.08.30
※当コンテンツの内容は2021年7月時点の情報となります。
新型コロナウイルス感染症にかかっていることを確かめるには、体内にウイルスがいるかどうか、あるいはいたかどうかを調べなければなりません。最も敏感な検査法はPCR検査です。治療については、まだ「抗コロナウイルス剤」というような特効薬はなく、起こっている症状や炎症を抑える治療が中心となっています。
監修:岡部信彦(川崎市健康安全研究所 参与)
検査は大きく分けて3種類。それぞれに特徴があります
PCR検査は、いま感染しているかどうかを確かめる検査として主に用いられる
感染を調べる主な検査は、「ウイルスの遺伝子」を検知するPCR法などの検査、「ウイルスの表面のたんぱく」を見つけ出してウイルスがいるかどうかを検知する抗原検査、生体がウイルスと戦った証拠、あるいはワクチン接種で体内にできた「抗体」を検知する抗体検査、「ウイルスそのもの」がいるかどうかを検知するウイルス培養法*、などがあります。
*ウイルス培養法は、特殊な設備や技術を要するため、一般的ではありません。
表1 PCR検査、抗原検査、抗体検査の違い
| 検査の種類 | PCR検査 | 抗原検査 | 抗体検査 |
|---|---|---|---|
| 調べるもの | ウイルスを構成する遺伝子配列の一部 | ウイルスの表面にあるたんぱく質(抗原) | 体がウイルスに反応してつくるたんぱく質(抗体) ワクチン接種によって体内にできた抗体 |
| 採取する検体 | 鼻咽頭・鼻腔ぬぐい液、だ液 | 鼻咽頭・鼻腔ぬぐい液、だ液 | 血液 |
| 何がわかるか | 現在、感染しているかどうか(ウイルスがいるかどうか) | 現在、感染しているかどうか(ウイルスがいるかどうか) | 過去に感染したことがあるかどうか |
| 特徴 | ほんの少しの量で検出。感染性がなくても陽性の場合あり | 検出には、一定以上のウイルス量が必要 PCR検査より検知する力が低い |
感染したことがあるかを把握し、予防対策に役立てられる |
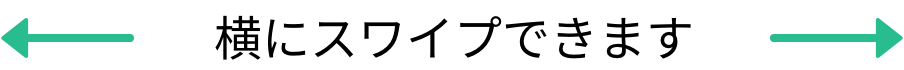
(テルモ作成)
PCR検査はウイルスを構成する遺伝子の一部を鋭敏に見つけ出すので、ほんのわずかのウイルスの断片があるだけでも陽性になります。したがって感染初期の、体内のウイルスがほんの少しの時でも検知できる一方、発病してから10日以上を経て体内のウイルスがほとんどいなくなっても、死滅したウイルスでもその遺伝子の一部が残っていれば検知できるので、回復しても長い間PCR検査が陽性となることがあります。つまりこの場合は人にうつるウイルスそのものはいなくなっても、うつる力を失ったウイルスの断片でも残っていればPCR検査が陽性になることになります。
ほかの人にうつす力があるかどうか(感染性)の判定は、PCR検査の結果だけでなく、症状が出てからの日数や、検査が初めて陽性になった時からの日数、症状の程度なども合わせて行われます。
短時間で結果が出る抗原検査。過去の感染を調べる抗体検査
いま感染しているかどうか、ウイルスがいるかどうかを調べる検査として、抗原検査があります。抗原検査は、約30分という短時間で結果がでます。PCR検査に比べると、ウイルスを検知する力が低いので、ある程度の量のウイルスがないと見逃す可能性がありますが、人にうつす程度のウイルスがいるときは大体陽性なります。
抗体検査は、過去に感染したことがあるかどうかを調べる検査です。抗体はウイルスなどの外敵が体内に入り込んだ時に起こる免疫反応によって作られる、敵を退治するための武器の一つです。抗体は、多くの場合、次に感染を受けた時に発病阻止のために働きます。ワクチンはウイルスの感染に代わって、生体に抗体を作らせる道具といえます。
新型コロナウイルスに直接作用する特効薬は現在のところなし。他のウイルスや病原体に効果のある薬剤を応用したり、炎症や症状を抑える薬剤を使用する。肺炎を起こすと、酸素、人工呼吸器、人工心肺装置などを程度に応じて使い分ける
新型コロナウイルス感染症には、まだ「抗コロナウイルス薬」のような新型コロナウイルスに直接強く作用する特効薬がありません。ただし、一定の効果が確認されているとして厚生労働省が認可している薬や、認可はまだされていないものの理論上効果がありそうなものについて、研究を目的とし、限られた医療機関で慎重に使われている薬がいくつかあります。
症状が出はじめ、ウイルスが次々と増殖していく時期には、ウイルスの増殖をできるだけ妨げる薬(抗ウイルス薬)が使われます。症状が重くなり、肺炎などの炎症が激しくなった時期には、炎症を抑える薬(抗炎症薬)が使われるのが、一般的な論理的な治療法です。
肺炎の症状が進み、酸素飽和度(酸素が血流に乗って体の末端まで行き届いているかを示す指標)が基準値を下回る状態になった場合は、酸素吸入をして呼吸をサポートします。さらに症状が悪化して、自分の力で十分に呼吸ができなくなった場合には、人工呼吸器で呼吸を助けます。それでも回復が見込めず、深刻な状態になった場合には、ECMO(エクモ;体外式膜型人工肺)と呼ばれる特殊な装置を使って、自分の肺の代わりに、器械に肺の働きをさせたりすることもあります。呼吸を助けたり、肺を休ませたりすることにより、肺の負担を減らし、自分の力で回復することを期待するものです。
監修者紹介

岡部信彦
川崎市健康安全研究所 参与
1971年、東京慈恵会医科大学卒業。同大学小児科で研修後、帝京大学小児科助手、その後、慈恵医大小児科助手。国立小児病院感染科、神奈川県立衛生看護専門学校付属病院小児科などに勤務。1991~1994年、世界保健機関(WHO)西太平洋地域事務局(フィリピン・マニラ市)伝染性疾患予防対策課課長。1994~1997年、慈恵医大小児科助教授。1997年、国立感染症研究所感染症情報センター・室長。2000年、同研究所感染症情報センター長。2012年から川崎市健康安全研究所 所長に就任し、2024年より現職。内閣官房新型コロナウイルス感染症対策分科会委員、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード委員を歴任。
- カテゴリ
- テーマ
- キーワード