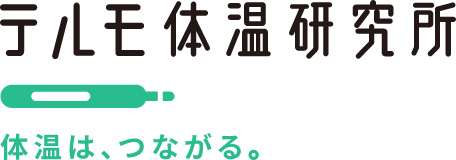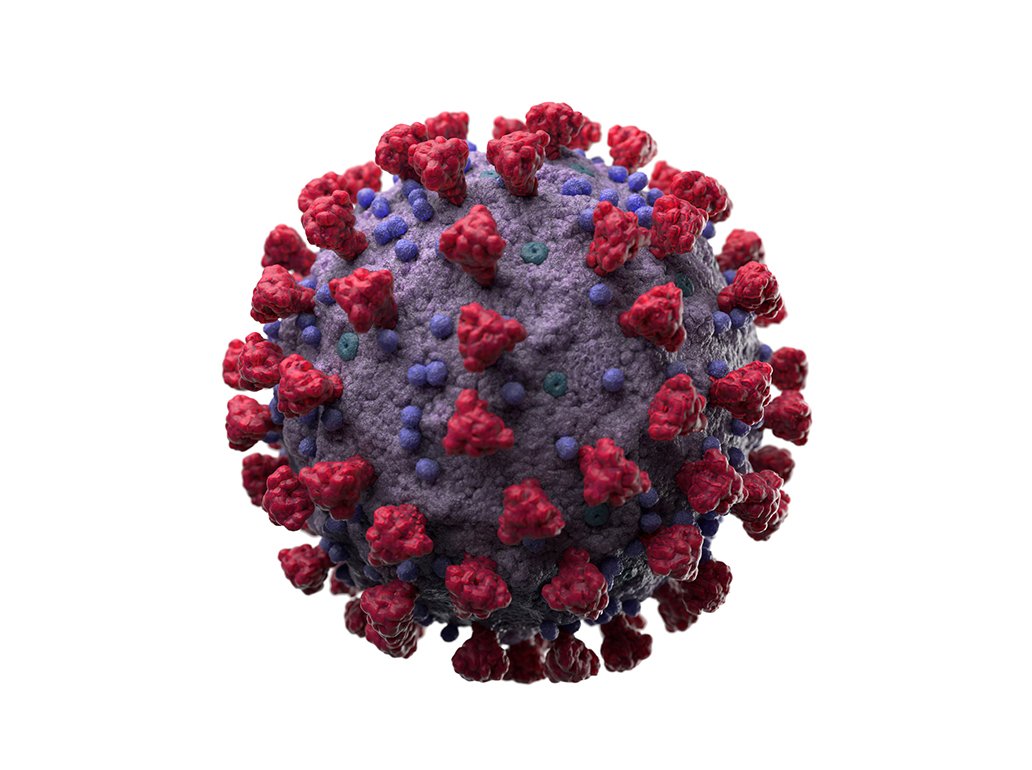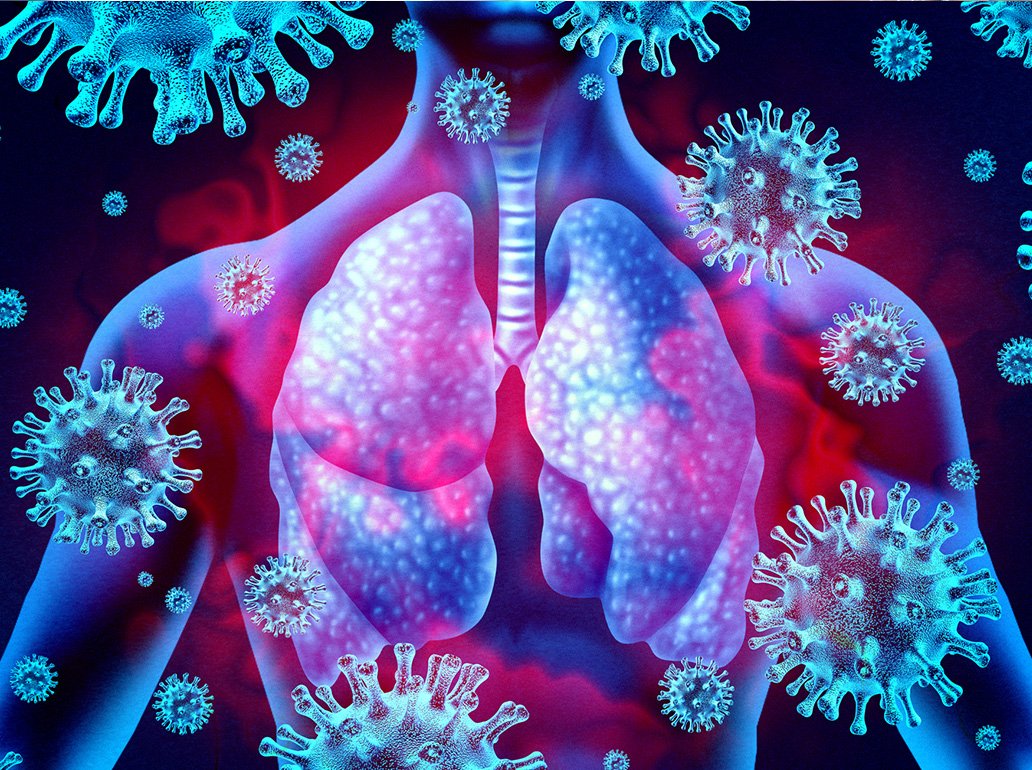- トップページ
- 発熱相談室
- 新型コロナウイルス感染症について
- 「新型コロナウイルス感染症」知っておきたいキーワード解説

「新型コロナウイルス感染症」知っておきたいキーワード解説
公開日2021.08.30
※当コンテンツの内容は2021年7月時点の情報となります。
新型コロナウイルス感染症についての解説では、聞きなれない言葉も少なくありません。関連するキーワードついて、特徴、検査、治療、予防、関連するかもしれない病気に分けて、簡単な解説を加えました。
監修:岡部信彦(川崎市健康安全研究所 参与)
目次
特徴
RNAウイルス
ウイルスの分類の一種。RNAとは(Ribonucleic Acid)の略。リボ核酸。ウイルスのたんぱく質をつくる設計図(遺伝情報)をRNAの形で持っているウイルスのこと。
新型コロナウイルスは、RNAウイルスに分類されます。DNAウイルスに比べてRNAウイルスは、遺伝情報を伝える際に一部の情報の伝達が誤って伝わるコピーミスが起こりやすい構造になっています。
新型コロナウイルスが変異しやすいのは、コピーミスが起こるためですが、そのまま何も起きないこともあれば、変異の部位や程度によって、感染力や病原性に変化が生じる場合もあります。
パンデミック(Pandemic)
感染症の世界的大流行のこと。地理的に広い範囲の世界的な流行および、非常に多くの数の感染者や患者を発生する流行を指します。新型コロナウイルス感染症では、2020年3月にWHO(世界保健機関)がパンデミックを表明しました。エイズなども、当初パンデミックと言われたこともあり、新たなインフルエンザウイルス(新型インフルエンザ)の世界的流行は「インフルエンザパンデミック」と言われます。
変異株
ウイルスの遺伝情報が変化したことにより、新しい性質を持ったものを変異株と呼んでいます。新型コロナウイルスは遺伝情報のコピーミス(遺伝情報の一部が誤って伝わる)により、変異しやすい性質を持っています。このため、世界中でさまざまな変異株が見つかっています。変異があるのは珍しい話ではないのですが、変異の部位や程度によって、感染力や病原性に変化が生じる場合もあり、専門家らは注意深くこれを見つけ出しています。
検査
抗原検査
ウイルス特有のたんぱく質(抗原)を見つけ出す検査法。鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、もしくは唾液で検査できます。
陰性か陽性かだけを判定する定性検査と、ウイルス量を数字で示す定量検査があります。手軽に行われるのは定性検査です。ウイルス量が少ないと陰性の判定をしてしまうことがあり、PCR検査に比べるとウイルスを検知する力が低いので、ある程度の量のウイルスがないと見逃す可能性がありますが、人にうつす程度のウイルスがいるときは大体陽性になります。
抗体検査
ウイルスに対する抗体(免疫)の有無を調べる検査法。抗体とは、ウイルスなど体に侵入した外敵を攻撃するために作られるたんぱく質です。少量の血液で判定することができます。抗体が見つかれば、過去に感染したことがあることになります。
抗体検査では、現在、感染しているかどうかはわかりません。抗体は多くの場合、次に感染を受けた時に発病阻止のために働きます。ワクチンはウイルスの感染に代わって、生体に抗体を作らせる道具といえます。
PCR検査(ピーシーアール検査)
PCRは、Polymerase Chain Reactionの略。調べたいウイルスの特徴的な遺伝子配列に着目し、見つけ出す方法です。ポリメラーゼという酵素を利用してウイルスの遺伝子のうち、着目した部分だけを増やして見つけやすくしているので、ウイルスの量がかなり少なくてもウイルスあるいはウイルスのかけらの有無がわかります。鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、もしくは唾液で検査できます。
PCR検査はウイルスを構成する遺伝子の一部を鋭敏に見つけ出すので、ほんのわずかのウイルスの断片があるだけでも陽性になります。したがって感染初期の、体内のウイルスがほんの少しの時でも検知できる一方、発病してから10日以上を経て体内のウイルスがほとんどいなくなっても、死滅したウイルスでもその遺伝子の一部が残っていれば検知できるので、回復しても長い間PCRが陽性となることがあります。
つまりこの場合は人にうつるウイルスそのものはいなくなっても、うつる力を失ったウイルスの断片でも残っていればPCR検査が陽性になることになります。
治療
ECMO(エクモ)
体外式膜型人工肺。extracorporeal membrane oxygenationの略。ガス交換をする人工肺(膜型人工肺)と、体内から血液を取り出し人工肺に血液を送り体内に送り戻す血液ポンプからできています。
人の肺の代わりに、人工肺を通じて酸素と二酸化炭素の交換(ガス交換)を行う治療に用いられます。
新型コロナウイルス感染症で最も重症化し、自力では必要な酸素を取り込めなくなった時の切り札ともいえるのが、ECMOです。ECMOによって直接新型コロナウイルスを攻撃できるわけではありませんが、肺の負担を軽くすることで、自力で治す力をサポートする役割を果たしています。
予防
三密
新型コロナウイルス感染症で、集団の感染を防ぐため、避けたほうがよいとされる環境。密閉空間・密集場所・密接場面を指します。WHOは「日本の三密を避ける」を採り入れて、2020年7月にCrowded places (人が集まる場所)、Close-contact settings (濃厚接触になる状況)、Confined and enclosed spaces (閉鎖かつ密閉された空間)の3Cを避けるよう呼びかけるメッセージを発信しています。
mRNA(メッセンジャー・アール・エヌ・エー)
細胞のなかで、たんぱく質を組み立てるための設計図。細胞の核内にあるDNAから作られ、タンパク質を作るのに利用された直後に分解されます。ヒトの細胞内では常にmRNAが作られています。新型コロナウイルスのワクチンでは、これまでとは異なった方法としてmRNAに注目し、ウイルスの特徴であるスパイクたんぱく質と呼ばれる外側のトゲトゲをつくる設計図を利用したワクチンが開発されました。
関連するかもしれない病気
川崎病
子どもに多くみられる病気の一つで、全身の血管で炎症が起きてしまうものです。高熱が出て、両目が赤く充血する、唇がカサカサと乾燥して赤くなる、手や足の指先から皮膚がむけるなどの症状が現れます。欧米で、新型コロナウイルス感染症にかかり、重症になった子どものなかに、この病気とよく似た症状がみられるという報告がされました。
ただし、日本の川崎病は、低年齢小児でよくみられるものです。欧米から報告される川崎病類似症状は、高年齢小児に起きており、日本の川崎病とは少し異なっているようです。
なお日本では、欧米で報告されたものに近い症状を示した報告は、これまでのところはありません。日本川崎病学会では、2020年5月、日本とアジア地域においての調査結果に基づき、日本や近隣国で見られている川崎病と新型コロナウイルス感染症との間に関連は認められないとの声明を発表しています。
日本川崎病学会の声明は(こちら)
http://www.jskd.jp/pdf/20200506COVID-19_and_KD.pdf
血栓症
さまざまな原因によって血管の中にできる血の塊を血栓といいます。血栓ができてしまう病気が血栓症です。新型コロナウイルス感染症で、重症化する人にみられる症状の一つです。血栓はできた場所から血流に乗っていろいろな臓器に飛ぶことがあります。肺に飛んでしまうと肺塞栓症、心臓であれば心筋梗塞、脳であれば脳梗塞となります。
監修者紹介

岡部信彦
川崎市健康安全研究所 参与
1971年、東京慈恵会医科大学卒業。同大学小児科で研修後、帝京大学小児科助手、その後、慈恵医大小児科助手。国立小児病院感染科、神奈川県立衛生看護専門学校付属病院小児科などに勤務。1991~1994年、世界保健機関(WHO)西太平洋地域事務局(フィリピン・マニラ市)伝染性疾患予防対策課課長。1994~1997年、慈恵医大小児科助教授。1997年、国立感染症研究所感染症情報センター・室長。2000年、同研究所感染症情報センター長。2012年から川崎市健康安全研究所 所長に就任し、2024年より現職。内閣官房新型コロナウイルス感染症対策分科会委員、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード委員を歴任。
- カテゴリ
- テーマ
- キーワード