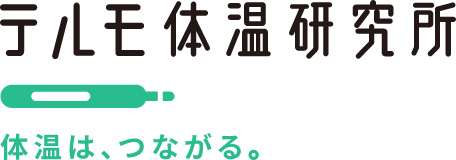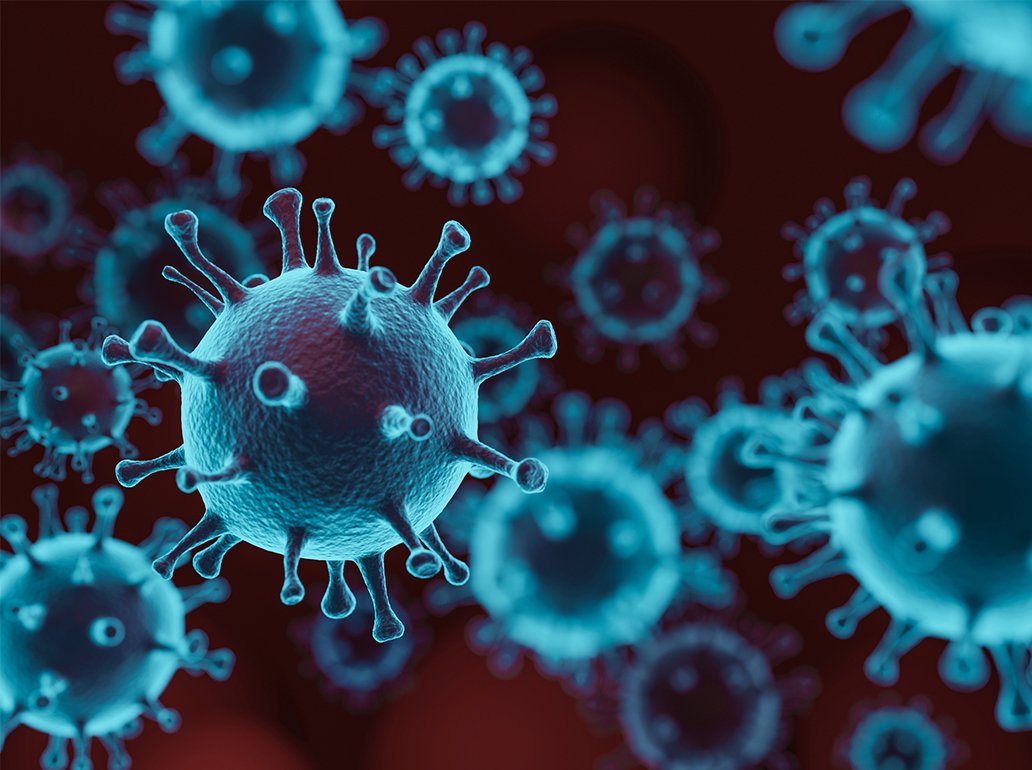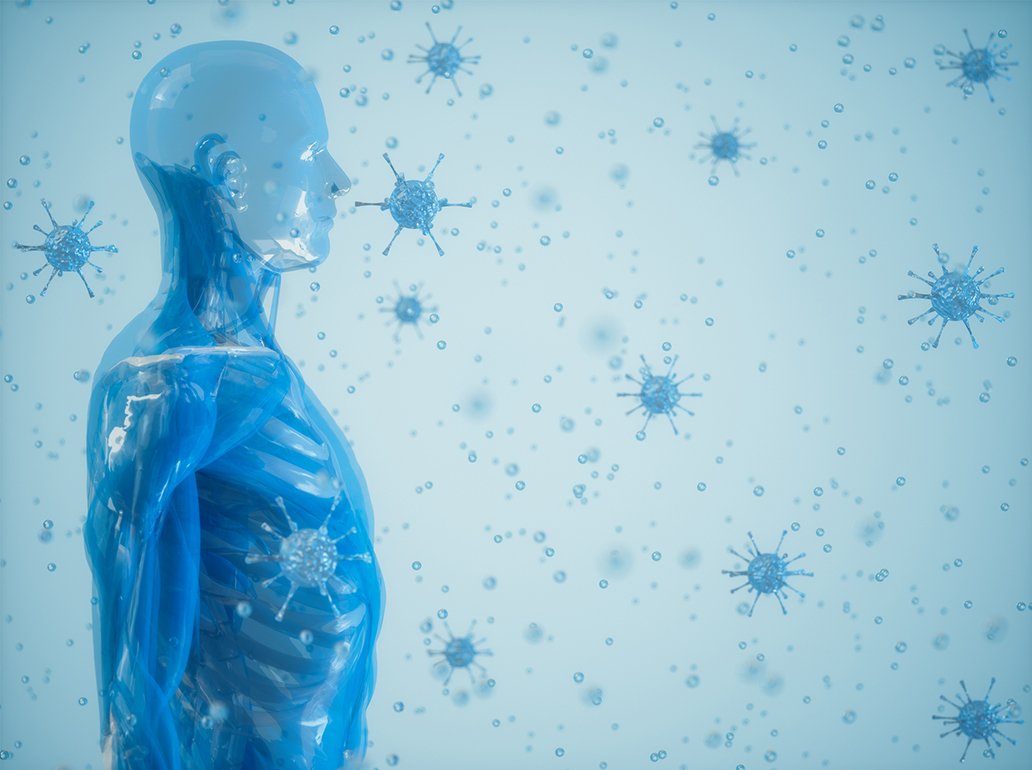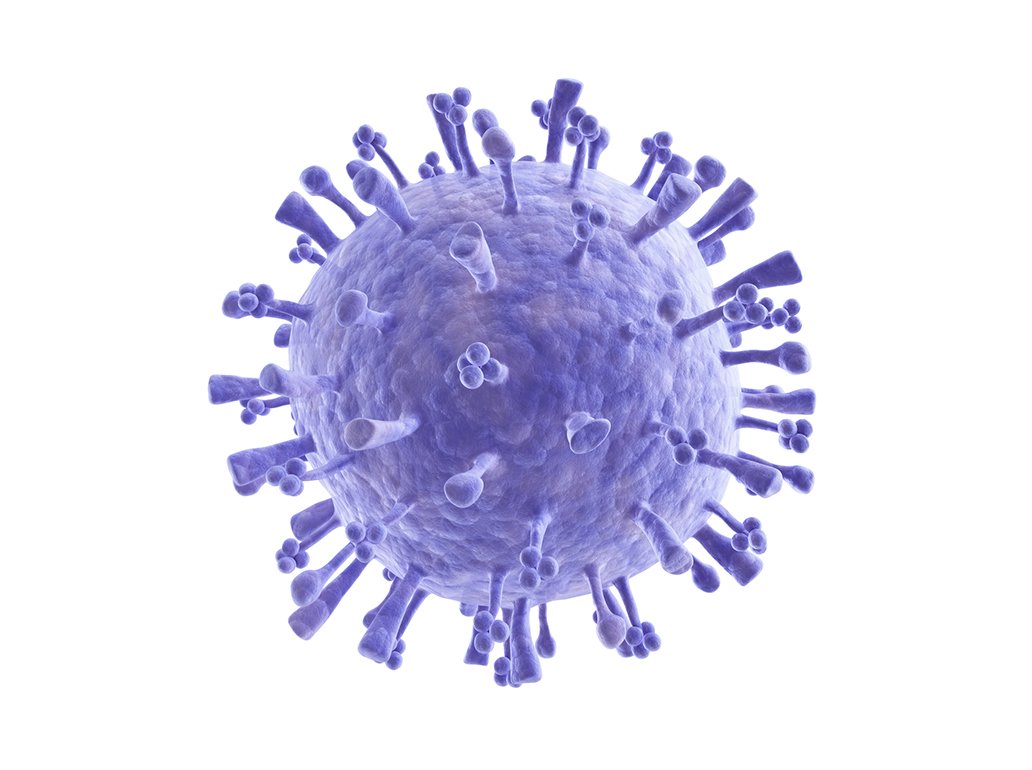かぜ
公開日2021.08.30
※当コンテンツの内容は2021年7月時点の情報となります。
かぜは、症状の変化に要注意。原因となるウイルスにも、多くの種類があります。かかったときは、休養と睡眠、水分補給が大切です。
監修:岡部信彦(川崎市健康安全研究所 参与)
目次
原因と経過
かぜは症状の変化に注意が必要
かぜは専門的には「かぜ症候群」と呼ばれ、いろいろな病因によって起こる鼻からのどまでの上気道の急性カタル性炎症(炎症によって多くの粘液が分泌される状態)を一括したものです。
かぜ症候群の80~90%はウイルスによるものとされます。
かぜ症候群の経過は急性でおよそ1週間であり、ウイルスによって症状に多少の違いがみられますが、自然に治ることが多く、予後は良好です。
しかし重い病気も最初はかぜのような症状から始まることが珍しくありません。無理はしないで、あまり長く症状が続くものや、症状が変化するものについては、注意が必要です。
<かぜのような症状で始まる病気の例>
急性気管支炎・・強いせきが続き、胸が痛くなる。
肺炎・・肺の奥までウイルスが入り込んで炎症を起こす。
おたふくかぜ・・ほっぺたがはれて、耳のうしろが大きくふくらむ。
はしか・・高熱のあと、体じゅうに赤いブツブツが出る。
咽頭結膜炎(プール熱)・・熱が出て、目が赤くなる。
子どもの発熱を伴う病気の詳しい情報は(こちら)
かぜを引き起こすウイルスには多くの種類がある
かぜのウイルスには非常に多くの種類がありますが、代表的なものは次のようなウイルスです。
- ライノウイルス
かぜの約半数がこのウイルスを原因として起こります。 - コロナウイルス
かぜの15~20%がこのウイルスを原因として起こります。
(これとは違う種類のコロナウイルスが、新型コロナウイルス感染症の原因ウイルス:SARS CoV-2です) - アデノウイルス
冬の終わりから春、初夏にも多く分離されます。咽頭結膜熱(プール熱といわれることある)の原因にもなります。 - パラインフルエンザウイルス、RSウイルス
成人ではふつうのかぜの原因ですが、子どもではクループや細気管支炎を起こすことがあります。新生児や乳児のRSウイルス感染は重症になりやすく要注意です。 - エンテロウイルス
夏に流行します。発疹や下痢、髄膜炎や、心膜炎などを起こすこともあります。
かぜをひいた時、守ってほしいこと
あまり無理をしないで休養をとりましょう。特に睡眠を十分にとることが大切です。
熱が出たら、水分を十分に補給しましょう。お茶、ジュース、スープなど飲みたいもので結構です。
症状の変化には十分気をつけてください。薬を飲む、飲まないにかかわらず、熱が出ている時、新たな症状が加わっていないか、いままでより悪化していないかなど様子の変化にはよく気をつけるようにしましょう。
かぜの予防法
いつも清潔に、体調管理をしっかり
かぜのワクチンはありません
かぜのウイルスには多くの種類があり、またそれぞれのウイルスは、時がたつにつれ少しずつ変化するため、かぜに有効なワクチンはまだ開発されていません。
衛生状態をよくしましょう
衛生面に気をつけることが最も基本的な予防法になります。かぜのウイルスは感染した人から出た唾液(だえき)などの分泌物に触れることで広がることもあります。外出から帰ったら、手を洗いましょう。
監修者紹介

岡部信彦
川崎市健康安全研究所 参与
1971年、東京慈恵会医科大学卒業。同大学小児科で研修後、帝京大学小児科助手、その後、慈恵医大小児科助手。国立小児病院感染科、神奈川県立衛生看護専門学校付属病院小児科などに勤務。1991~1994年、世界保健機関(WHO)西太平洋地域事務局(フィリピン・マニラ市)伝染性疾患予防対策課課長。1994~1997年、慈恵医大小児科助教授。1997年、国立感染症研究所感染症情報センター・室長。2000年、同研究所感染症情報センター長。2012年から川崎市健康安全研究所 所長に就任し、2024年より現職。内閣官房新型コロナウイルス感染症対策分科会委員、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード委員を歴任。
- カテゴリ
- テーマ
- キーワード