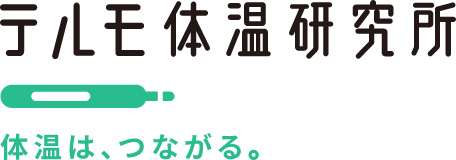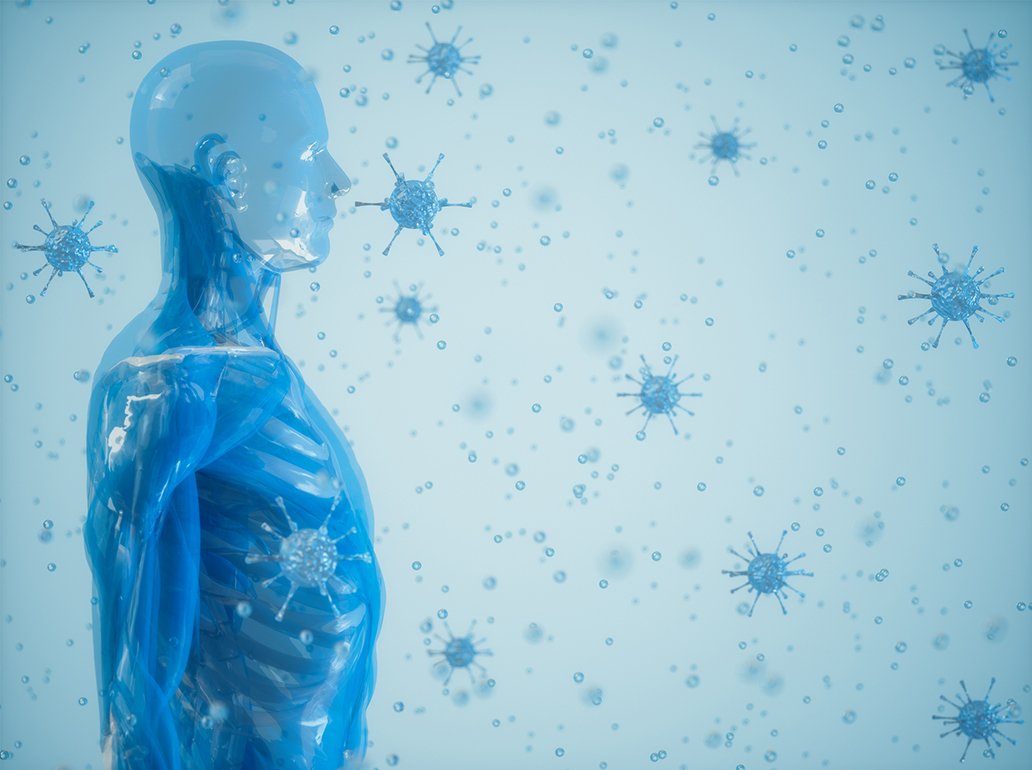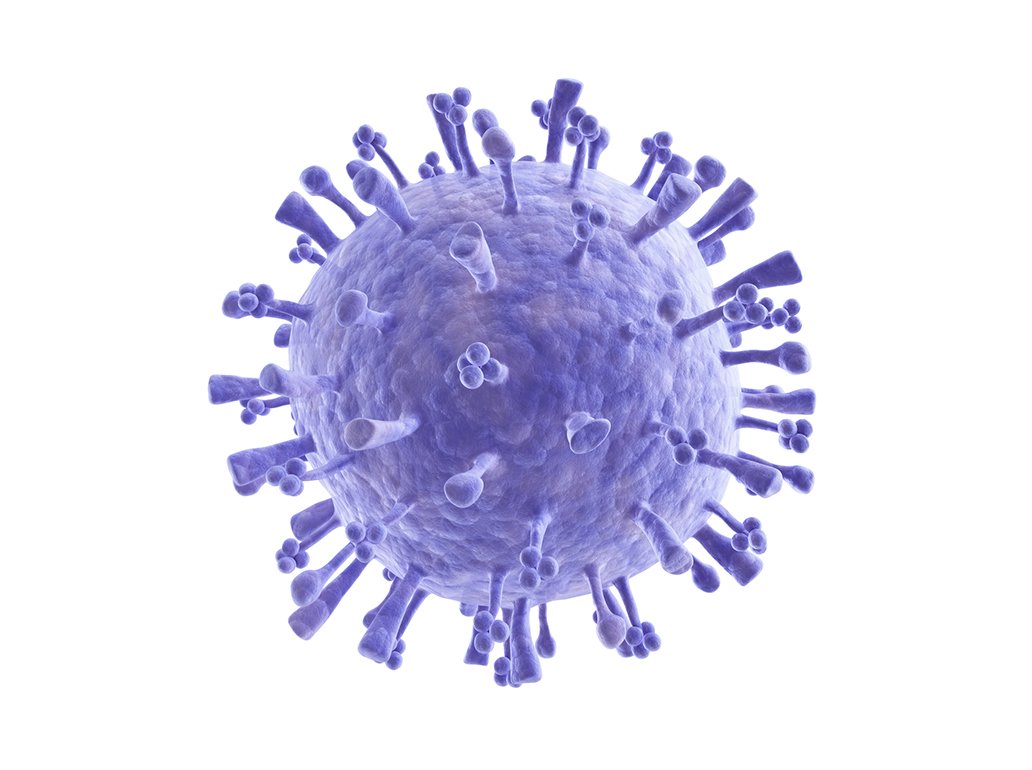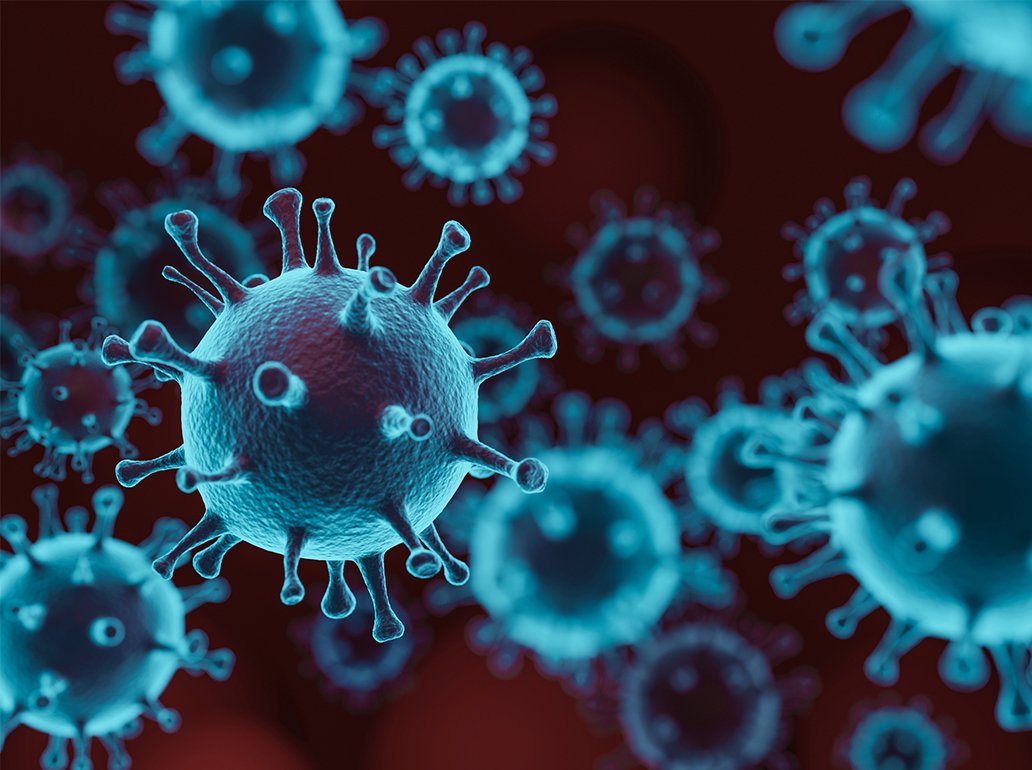
感染症とは
公開日2021.08.30
※当コンテンツの内容は2021年7月時点の情報となります。
病原体の感染によってさまざまな症状が引き起こされる病気をまとめて感染症と呼びます。
監修:岡部信彦(川崎市健康安全研究所 参与)
病原体の種類、感染経路、法律による取り扱いなどによって分けられる
代表的な小さな病原体は、目に見えない細菌やウイルス。目に見える病原体は寄生虫など
感染症の多くは、目に見えない小さな生物(微生物)が体の中に侵入することによって、発熱をはじめ、下痢、せきなどのさまざまな症状が現れる病気です。
病気を引き起こす微生物を病原体といいますが、病原体は、大きさや構造の違いから、細菌、ウイルス、真菌(かび)、寄生虫などに分けられます。ふだん、よくみられる感染症のほとんどは、細菌またはウイルスの感染によるものです。
細菌もウイルスも目に見えないほど小さい生物です。細菌の大きさは、1~5μm(マイクロメートル)。1μmは1,000分の1mmです。
一方、ウイルスの大きさは、10~400nm(ナノメートル)。1nmは100万分の1mmです。細菌とウイルスの大きさを比べると、細菌はウイルスの約100倍の大きさで、ウイルスから見ると、細菌は巨大な生き物ということになります。
また、細菌は栄養さえあれば、自分で数を増やす(増殖する)ことができますが、ウイルスは自分だけでは増殖することができません。宿主といって、人や動物の細胞に住み着き、その細胞を利用して増えていきます。
表1 細菌・ウイルスが引き起こす主な主な感染症
| 大きさ | 性質 | 代表的な病気 |
|---|---|---|
| 細菌 1~5μm(マイクロメートル:1000 分の 1mm)程度 |
栄養さえあれば自分で増えることができる | 結核、A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎、百日咳、とびひ、サルモネラ菌などの食中毒、腸管出血性大腸菌感染症(O157、O26等)など |
| ウイルス 10~400nm(ナノメートル:100 万分の 1mm)程度" |
他の生物の細胞の中に入り込まなければ増えることはできない | 麻疹、水痘、風疹、流行性耳下腺炎、手足口病、インフルエンザ、咽頭結膜熱、ウイルス性肝炎、突発性発疹、伝染性紅斑、感染性胃腸炎 (ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス)、RSウイルス感染症、新型コロナ感染症など |
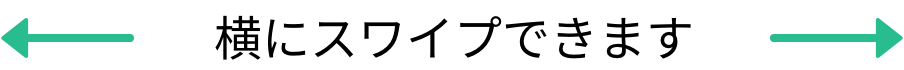
その他の病原体として、真菌、寄生虫、クラミジア、リケッチア、スピロヘータ、原虫などがあります。
感染しても症状が出ない場合も
病原体は、体内に入り込んでどんどん数を増やします。病原体が体に入り込むことを感染といいます。感染しただけでは病気になったとは限りません。その病原体が体の中で数を増やし続け、臓器や組織などを壊しさまざまな異常(症状)となって現れるのが発症です。
このように、感染と発症は意味合いが違います。感染して発症する場合もあれば、感染しても発症しない場合もあります。
病原体が持つ病気を引き起こす力と、人間が持つ病原体をやっつける力(免疫力)とのバランスで、病原体の力が勝れば症状が現れ、免疫の力が勝れば症状が出ないですむことになります。
病原体によっては、非常に強い力を持ち、一度かかると治りにくかったり、時には命にかかわるほどの症状に苦しまされたりする感染症もあります。
感染経路もいくつかある
病原体が人の体に入り込んでくる主な経路(人から人へ)は、接触感染、飛沫感染、空気感染などです。病原体によって、感染経路が決まっています。
接触感染
病原体に汚染されている物や人、病原体のついた手で誰かが触った物や場所など(ドアノブや手すりなど)を、ほかの人が触って、その手で口や鼻、
目などを触ると、粘膜から体内へ入りこみ感染します。
・細 菌 : 黄色ブドウ球菌、腸管出血性大腸菌など
・ウイルス: RSウイルス、エンテロウイルス、アデノウイルス、ロタウイルス、ノロウイルス、水痘・帯状疱疹ウイルス、新型コロナウイルスなど
飛沫感染
感染している人のせきやくしゃみ、つばなどに含まれている病原体をほかの人が吸いこむことで体のなかに取り込んでしまい、感染します。
・細 菌 : A群溶血性レンサ球菌、百日咳菌、インフルエンザ菌1)、マイコプラズマなど
・ウイルス: インフルエンザウイルス、アデノウイルス、風しんウイルス、ムンプスウイルス、水痘・帯状疱疹ウイルス、新型コロナウイルスなど
1) インフルエンザ菌とインフルエンザウイルスは別物です。冬に流行する病気としてなじみ深いインフルエンザは、インフルエンザウイルスによって引き起こされるものです。インフルエンザ菌は細菌の一つで、子どもの髄膜炎、大人の気管支炎や肺炎の原因となります。
空気感染
感染している人がせきやくしゃみをしたときに、口から飛び出した飛沫の水分が蒸発して、水分につつみ込まれていた病原体(飛沫核)が微小な粒子であるエアロゾルとなって空気中に漂い、それを吸い込んでしまうことで感染します。病原体は一定の時間漂い続けるので、同室(閉じられた空間)にいるだけで、感染の可能性があります。
・細 菌 : 結核菌
・ウイルス: 麻しんウイルス、水痘・帯状疱疹ウイルス
最近は、飛沫感染と空気感染の中間のようなマイクロエアロゾル感染という考え方もあります。新型コロナウイルスなどはマイクロエアロゾルによる感染もあり得ると考えられています。
このほか、人以外からの感染として、病原体を含んだ食べ物から感染する経口感染(主に黄色ブドウ球菌、腸管出血性大腸菌などによる食中毒など)、傷口からの感染(狂犬病ウイルス、破傷風など)、虫に刺されることで感染(マラリア原虫、デングウイルス、ジカウイルスなど)などがあります。
法律による分類がある
海外では、数十年前から新たな感染症が発生したり、また、日本では流行していなくても感染が拡大したりしている感染症がみられます。
そうした感染症のなかには、本来、日本国内に存在しない病原体に海外で感染して国内で発症したり、海外から持ち込まれた病原体に感染したりすることで発生する感染症を輸入感染症と呼びます。
病原体に国境はありません。そこで、海外の流行状況などによっては国内での感染を防ぐために、入国や出国を制限するといった強い対策が必要になる場合もあります。
そうした公衆衛生を守るための対策のもとになるのが感染症法であり、症状の重さや病原体の感染力などから一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症および新感染症の7種類に分類されています。新型コロナウイルス感染症は、2021年6月現在、指定感染症に分類されています。
表2 感染症法に基づく分類
| 分類 | 病気 |
|---|---|
| 1類感染症 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘(とう)そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱 |
| 2類感染症 | 急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ(H5N1およびH7N9) |
| 3類感染症 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス |
| 4類感染症 | E型肝炎、A型肝炎、狂犬病、ジカウイルス感染症、デング熱、日本脳炎、マラリア、レジオネラ症など |
| 5類感染症 | ウイルス性肝炎(A型・E型を除く)、後天性免疫不全症候群(エイズ)、先天性風しん症候群、梅毒、破傷風、百日咳、風しん、麻しんなど |
| 新型インフルエンザ等感染症 | 新型インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症など |
| 新感染症、指定感染症 | 現在は該当なし |
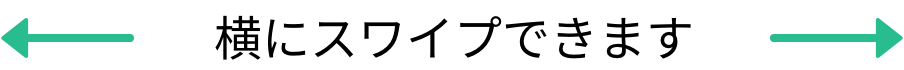
厚生労働省 感染症法における分類一覧(令和3年3月3日改正)に基づき作成
監修者紹介

岡部信彦
川崎市健康安全研究所 参与
1971年、東京慈恵会医科大学卒業。同大学小児科で研修後、帝京大学小児科助手、その後、慈恵医大小児科助手。国立小児病院感染科、神奈川県立衛生看護専門学校付属病院小児科などに勤務。1991~1994年、世界保健機関(WHO)西太平洋地域事務局(フィリピン・マニラ市)伝染性疾患予防対策課課長。1994~1997年、慈恵医大小児科助教授。1997年、国立感染症研究所感染症情報センター・室長。2000年、同研究所感染症情報センター長。2012年から川崎市健康安全研究所 所長に就任し、2024年より現職。内閣官房新型コロナウイルス感染症対策分科会委員、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード委員を歴任。
- カテゴリ
- テーマ
- キーワード