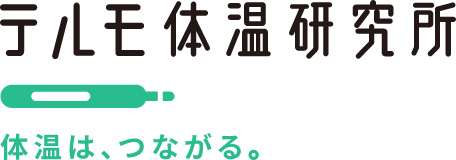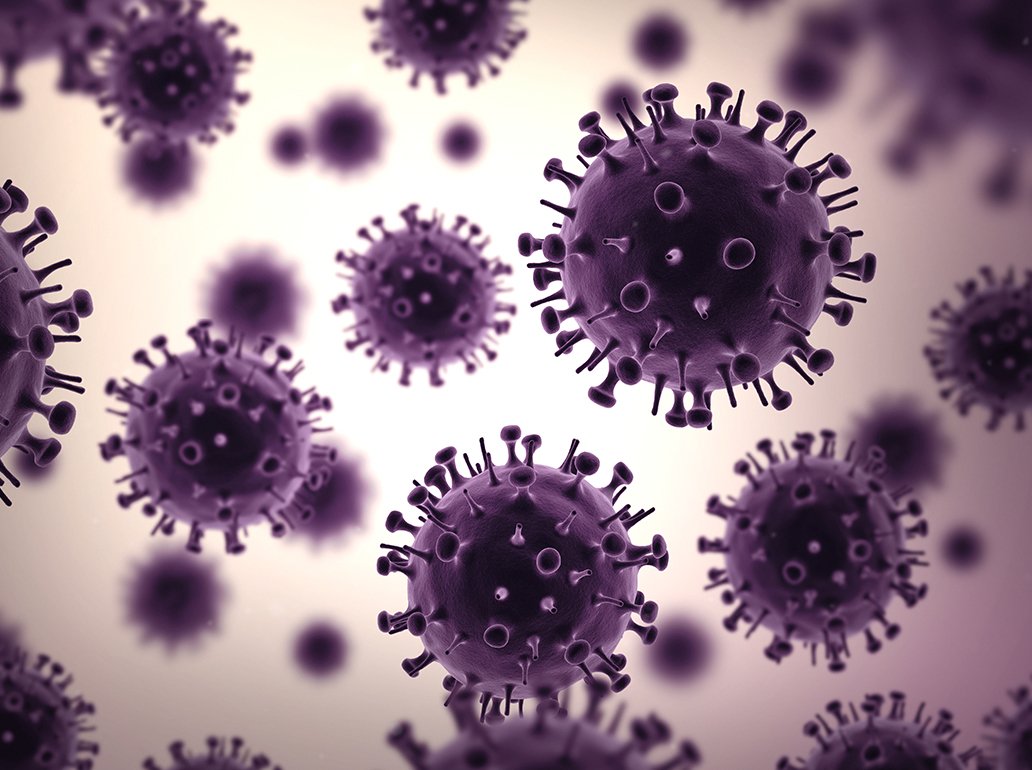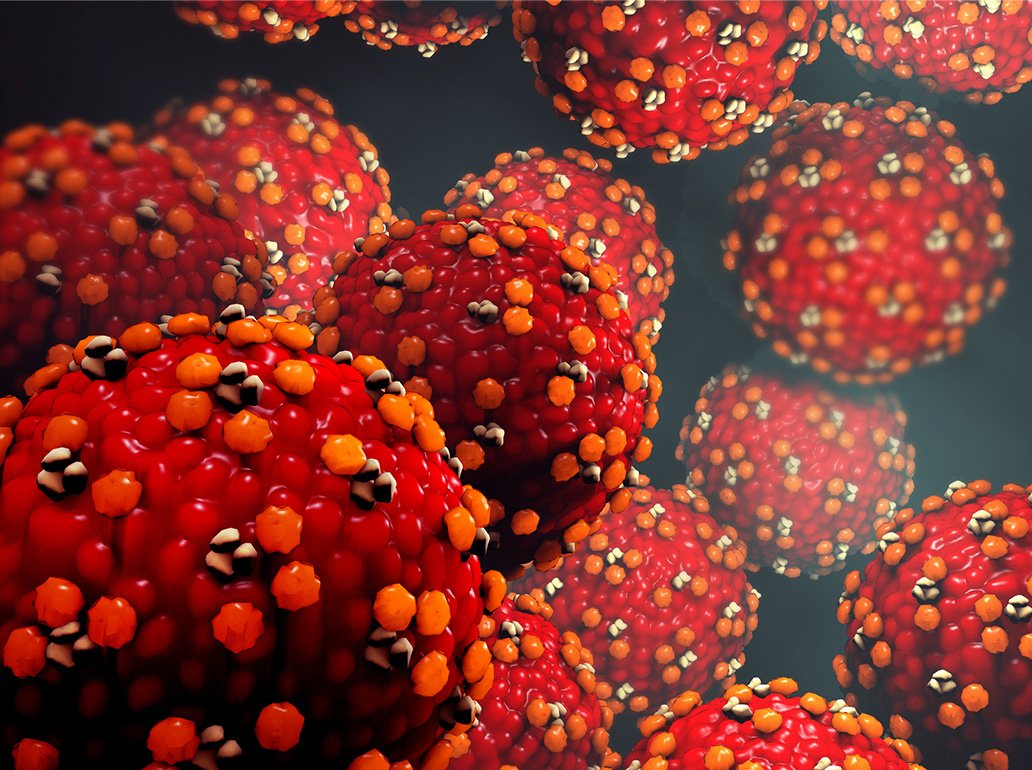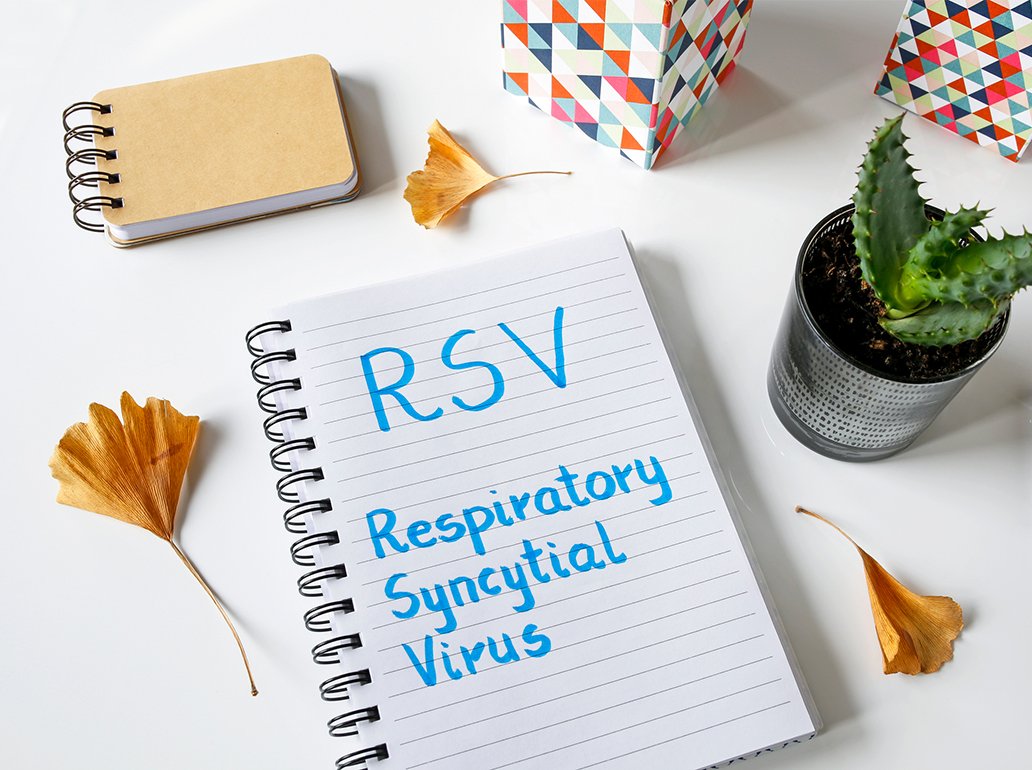
子どもの熱が出る病気:RSウイルス感染症
公開日2021.08.30
※当コンテンツの内容は2022年11月時点の情報で更新しました。
監修:草川功(東京都市大学人間科学部 特任教授)
目次
どんな病気?
RSウイルス感染症は、RSウイルスに接触感染や飛沫感染することによって起こる病気です。
流行する時期は、地域によって違いますが、近年は6-7月頃に流行が始まり半年くらい続きます。母親からもらう免疫が効かないため、生後6カ月未満でも発症することがあります。2~3歳ころまでにすべての子どもがかかるといわれています。
一度RSウイルスにかかったとしても、一生涯の免疫が得られるわけではないため、成人になるまでに何度もRSウイルスにかかる可能性はあります。
どんな症状?
発熱、鼻水、咳などが2~3日続きます。大人のように再感染の場合は、鼻水や咳程度の軽い感冒症状(かぜのような症状)で済むことがほとんどですが、1歳以下、特に3カ月未満の赤ちゃんで初感染の場合は細気管支炎や肺炎などを引き起こしやすいので注意が必要です。
ゼーゼーという喘鳴(ぜんめい)があったり、顔色や唇の色が悪かったり、呼吸の際に胸がペコペコへこむようなときはすぐに受診しましょう。
治療・ケア
特別な治療薬はなく、解熱剤や去痰薬などで症状を和らげます。合併症の疑いがあるときは抗菌薬が処方されることもあります。
家庭では咳を抑えるために、部屋を加湿します。脱水を防ぐために小まめな水分補給も大切です。
注:小さく生まれた赤ちゃん、心臓の病気を持った赤ちゃんなどには、RSウイルス感染の予防薬の注射があります。
<本記事における下記のことばの定義>
「乳児」・・1歳未満
「幼児」・・満1歳から小学校就学前まで
※参考:児童福祉法
監修者紹介

草川功
東京都市大学人間科学部 特任教授
東京医科大学病院小児科、東京医科大学八王子医療センター小児科、国立小児病院麻酔集中治療科、米国ピッツバーグ小児病院麻酔科・呼吸生理研究室、東京医科大学病院新生児部門などを経て1992年より聖路加国際病院小児科。2005年より同病院小児科医長、2022年より同病院診療教育アドバイザーを歴任。2025年より現職。公益法人全国保育サービス協会会長を兼任。
- カテゴリ
- テーマ