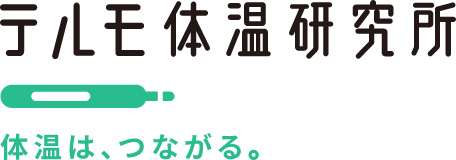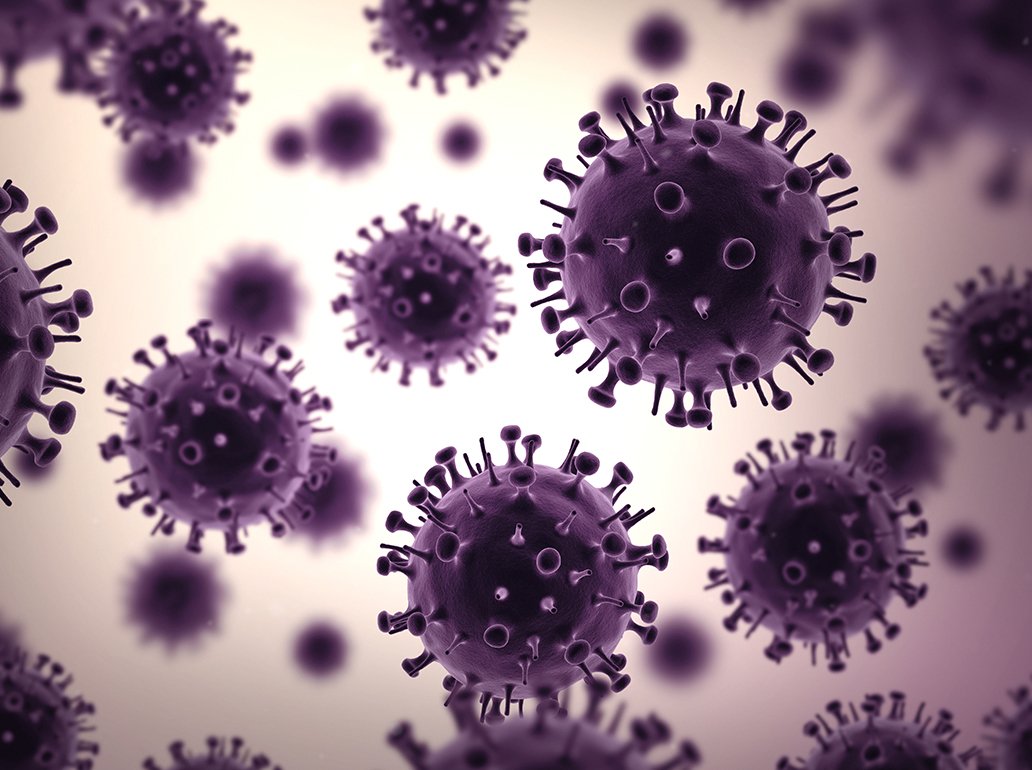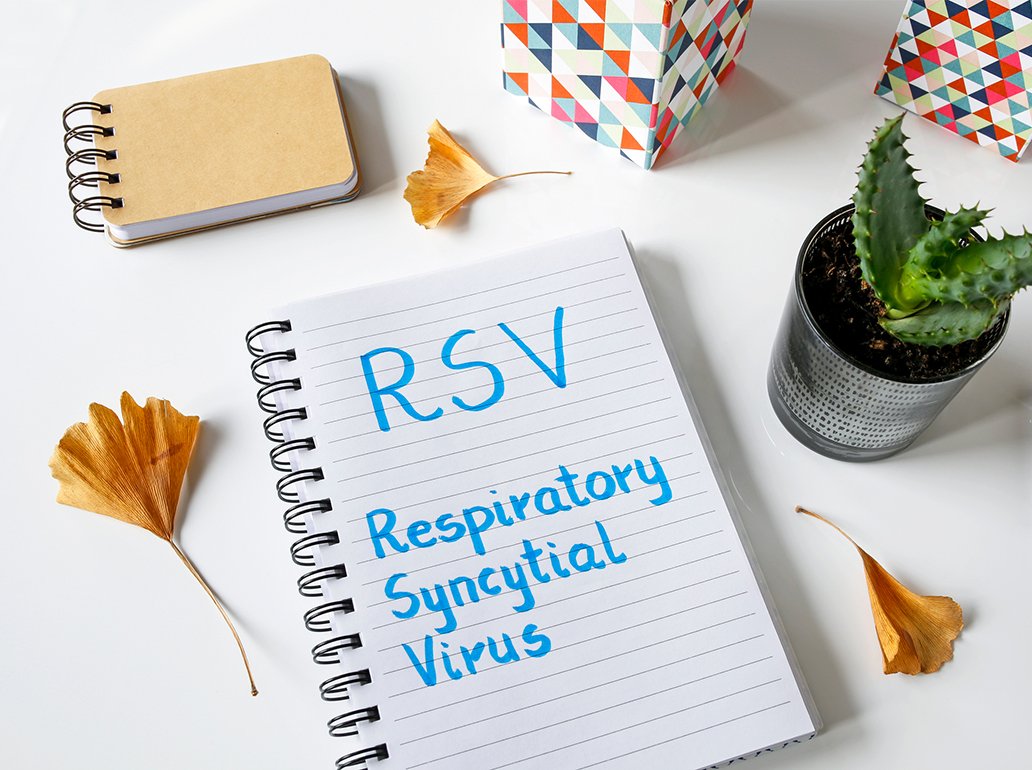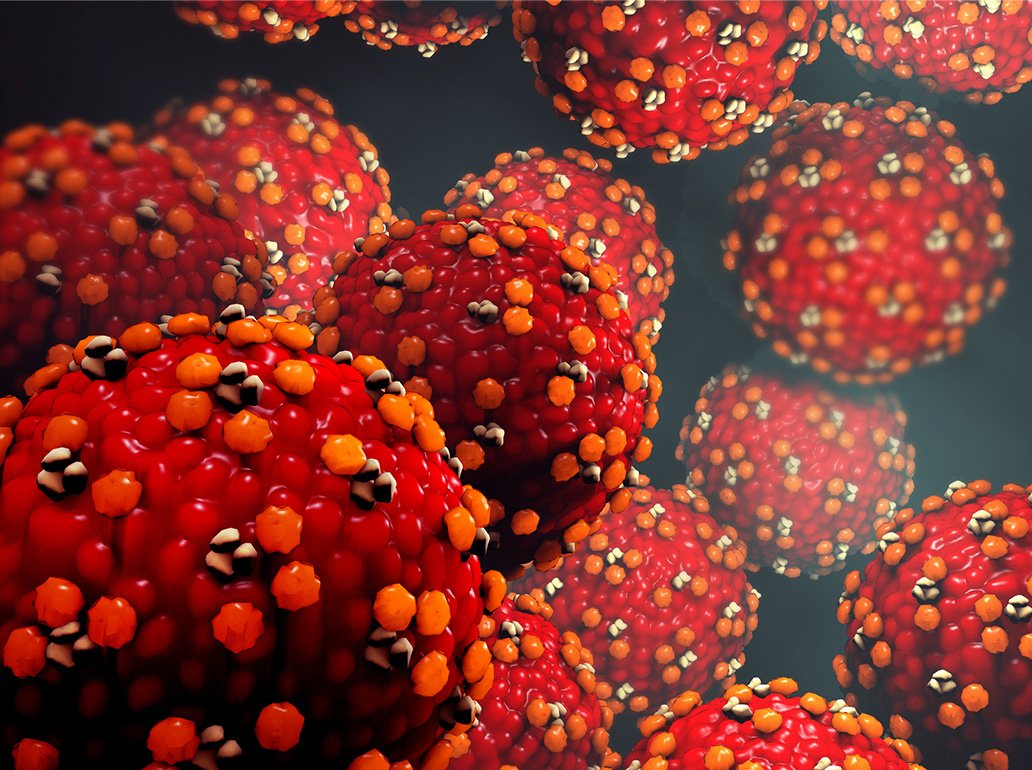子どもの熱が出る病気:尿路感染症
公開日2021.08.30
※当コンテンツの内容は2022年11月時点の情報で更新しました。
監修:草川功(東京都市大学人間科学部 特任教授)
目次
どんな病気?
尿をつくり体の外に排泄するまでの通り道=尿路(にょうろ)は、そこを流れる尿も含めて、通常は無菌状態に保たれています。しかし、なんらかの原因で尿路に病原体(細菌・ウイルス・真菌)が侵入し、炎症を起こしてしまうことがあり、これを尿路感染症といいます。
細菌が原因であることが最も多く、とくに原因となる菌は「大腸菌」で、尿路感染症を引き起こす原因菌のおよそ8割は大腸菌です。感染経路としては、尿の流れとは逆の方向に侵入してくることがほとんどです。
尿路感染症は男児も女児も赤ちゃんでもかかる可能性のある病気で、1歳までは比較的男児に多くみられますが、1~2歳以降は男女比が1:10と圧倒的に女児に多くなります。これは、女児の尿道が太く短く、細菌が外から侵入しやすいためだと考えられます。
どんな症状?
膀胱(ぼうこう)に感染した場合は膀胱炎、腎盂(じんう)に感染した場合は腎盂腎炎と呼び方が変わります。低月齢の赤ちゃんが繰り返して起こすときは、先天性のトラブルが隠れている可能性があるので、専門医の検査を受けることが必要です。
<膀胱炎>
排尿の際に痛がったり、尿の回数が増えたりします。一般的に発熱はないとされています。
<腎盂腎炎>
突然、38℃以上の発熱がありますが、咳や鼻水などの症状は出ません。排尿痛を伴うことがあり、赤ちゃんは母乳・ミルクの飲みが悪くなったり、泣くことが増えたりします。
症状が進むと脱水症状が現れたり、尿管や腎臓などに障害が出たりすることがあります。発熱だけでかぜの症状がない場合は、受診しましょう。
治療・ケア
膀胱炎では抗菌薬を服用し、多く水分をとって、尿をたくさん出して病原体を洗い流します。
比較的、短期間で治ります。腎盂腎炎では基本的に入院し、抗菌薬の点滴投与を行います。
感染を防ぐには、水分を十分にとって、体を清潔に保つことが大切です。女の子の赤ちゃんの場合は、うんちのときに前から後ろに拭いてあげましょう。
監修者紹介

草川功
東京都市大学人間科学部 特任教授
東京医科大学病院小児科、東京医科大学八王子医療センター小児科、国立小児病院麻酔集中治療科、米国ピッツバーグ小児病院麻酔科・呼吸生理研究室、東京医科大学病院新生児部門などを経て1992年より聖路加国際病院小児科。2005年より同病院小児科医長、2022年より同病院診療教育アドバイザーを歴任。2025年より現職。公益法人全国保育サービス協会会長を兼任。
- カテゴリ
- テーマ