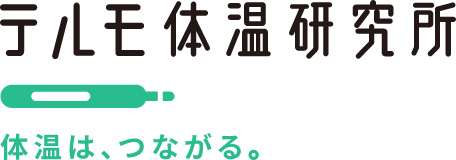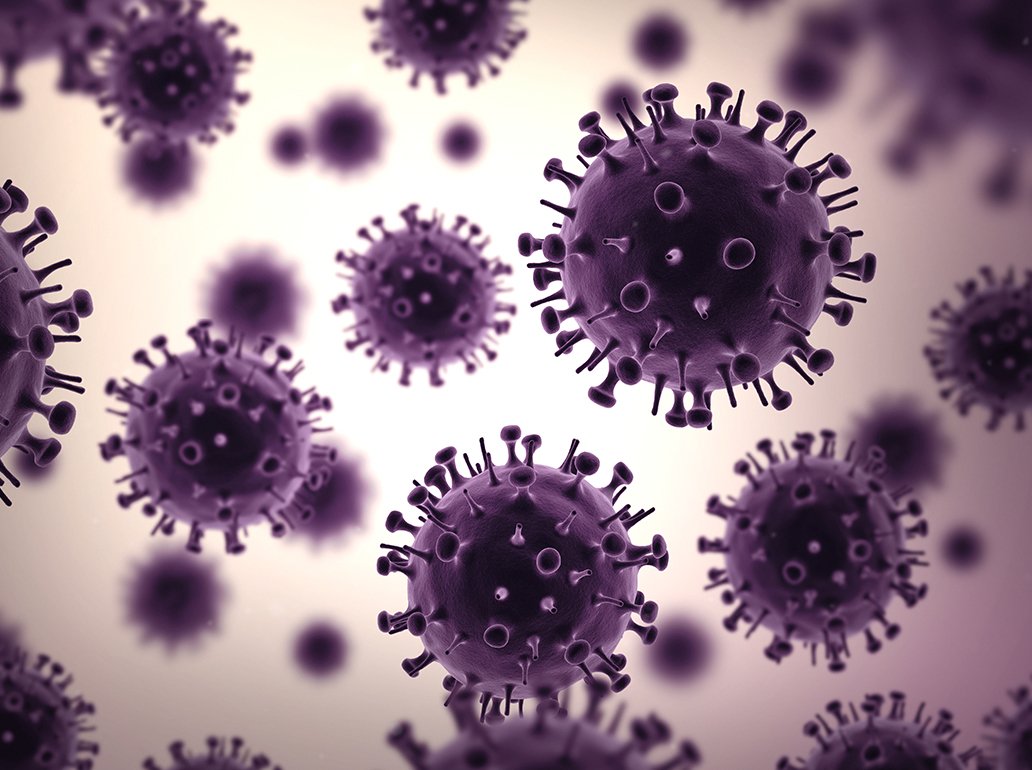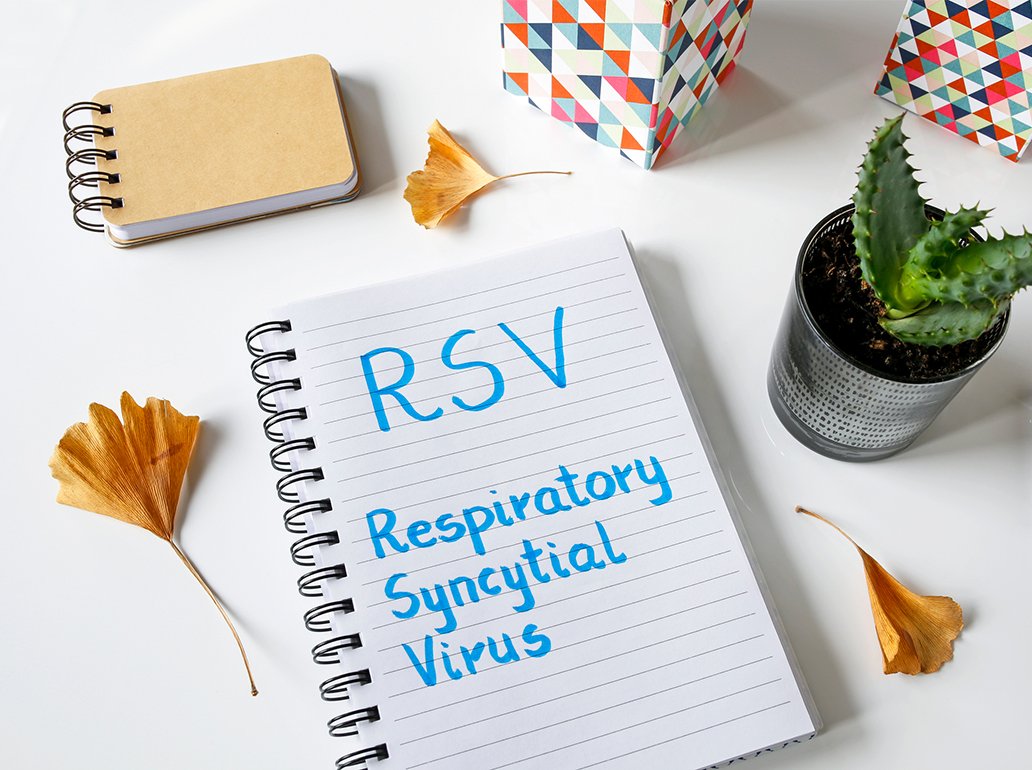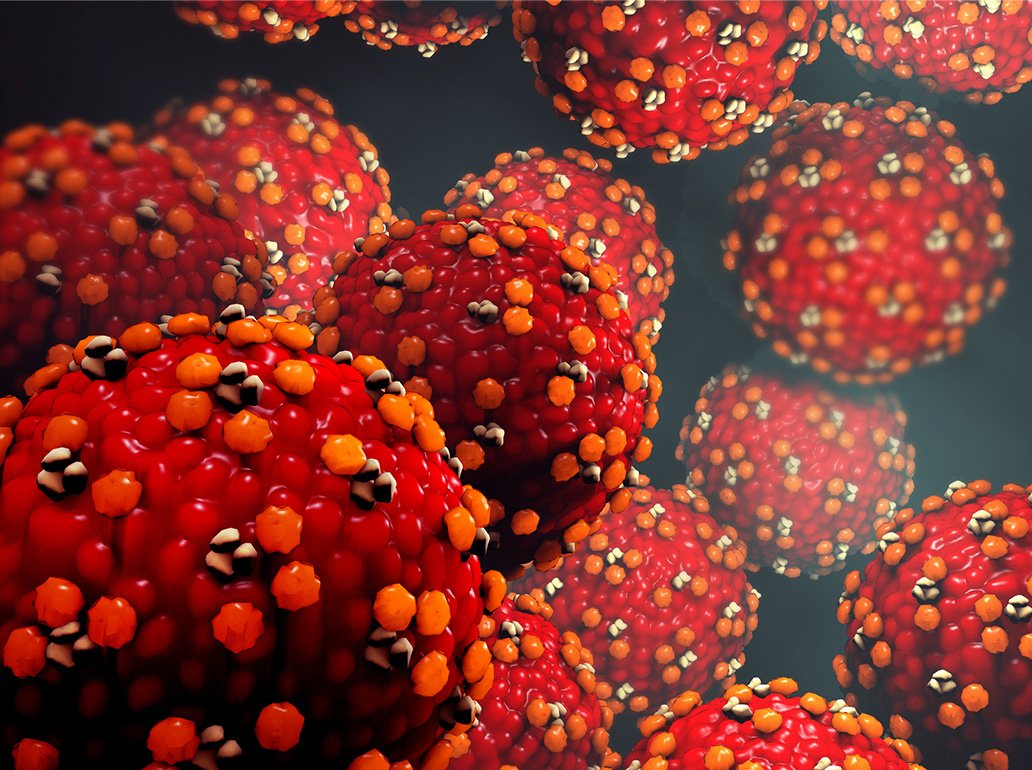子どもの熱が出る病気:おたふくかぜ
公開日2021.08.30
※当コンテンツの内容は2022年11月時点の情報で更新しました。
監修:草川功(東京都市大学人間科学部 特任教授)
目次
どんな病気?
おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)は、ムンプスウイルスに飛沫感染や接触感染することで引き起こされる病気です。
耳の下に位置し、唾液をつくる耳下腺(じかせん)に炎症が生じ、両側が腫れた場合におたふくのように見えることから「おたふくかぜ」と呼ばれます。発症した場合は、両側が腫れることが多いですが、片側のみしか腫れない場合もあります。
おたふくかぜは、保育所や幼稚園などで集団生活を開始したばかりの子どもに多く見られ、6歳までの子どもが発症例の半数以上を占めるとされています。一度、感染すれば生涯の免疫が獲得されますが、中には成人になってから初めておたふくかぜにかかる人もいます。
予防接種の普及により、発症する子どもは非常に減っています。
どんな症状?
最初の1~3日はあごを動かすだけでも痛みます。通常は大きな合併症もなく、自然に治癒することが多い病気ですが、頭痛や吐き気を伴う髄膜炎の合併症が知られています。
ときに難聴などの原因になることがあり、難聴は発症すると完治が難しいため、罹患を防ぐために1歳を過ぎたら早く予防接種を受けることが大切です。
治療・ケア
特別な治療薬はなく、熱や痛みを抑える薬が出されます。高熱が出るので、脱水を起こさないように小まめな水分補給が大切です。食事はのどの刺激となるような熱いものや酸っぱいものは避け、のどごしのよいものを用意しましょう。
監修者紹介

草川功
東京都市大学人間科学部 特任教授
東京医科大学病院小児科、東京医科大学八王子医療センター小児科、国立小児病院麻酔集中治療科、米国ピッツバーグ小児病院麻酔科・呼吸生理研究室、東京医科大学病院新生児部門などを経て1992年より聖路加国際病院小児科。2005年より同病院小児科医長、2022年より同病院診療教育アドバイザーを歴任。2025年より現職。公益法人全国保育サービス協会会長を兼任。
- カテゴリ
- テーマ